その日の昼休みは1人で骨董屋にはいかずに、仕事終わりに大山と一緒に行くことにした。
前回一人で行って失敗した達也は、大山を同行させることが、何かを変えるための重要な要素になるかもしれない、と考えたからだ。
「よう、早く行こうぜ。あの骨董屋、見に行こう」
「ああ、行こう。でも、もしシャッターが閉まっていても、絶対に店の周囲を離れるな」
達也の真剣な表情に、大山は戸惑いながらも頷いた。
夕暮れの中、二人は路地へ入った。やはり、骨董屋「時の音」のシャッターは固く閉まっていた。
「ずいぶん早い閉店時間だな」大山は落胆したような声で言った。
「仕方ない。少しここで待っていてくれないか」達也はそう言い残し、店の裏手に回った。
裏手は、雑草が生い茂る小さな空き地である。達也は、店の裏口を凝視した。
店主が言った「水の流れ」のヒントから、達也は一つの可能性に思い至っていた。
「仕組みは、私も分かりません」
店主は、本当に時計の仕組みを知らないのではないか。店主もまた、先祖から受け継いだ秘密の管理者であり、時計を扱うためのマニュアルを受け継いでいるだけではないか。
そして、そのマニュアルが、店主が「水の流れ」の原理を説明した時に使われた、あの透明なパイプのように、日常の中に隠されているのではないか。
達也は、店の壁に沿って、指でなぞるように歩いた。
古いレンガ造りの壁は、蔦が絡まり、一部が苔むしている。達也は、裏口から数メートル離れた、膝ほどの高さの壁の一部で足を止めた。
そこには、蔦に覆われてほとんど見えないが、真鍮製の、錆びた小さな水道の蛇口が取り付けられていた。水道管は壁の中に埋まっているようだ。

達也は、注意深く蔦を払い、蛇口を握った。冷たい真鍮の感触。
「水の流れを……」
達也は意を決して、蛇口を反時計回りに、ゆっくりと回した。
キーッ……という古びた音が響き、蛇口から少量の水が滲み出た。しかし、すぐに水は止まった。
達也はもう一度、強く蛇口を回した。
その瞬間、達也の足元の地面がゴゴゴ……と鈍い音を立てて振動した。
店の裏口から、左側の壁の一部が、まるで観音開きのように内側へ音もなく開き始めたのだ。
シャッターが閉まった骨董店の、もう一つの隠された入り口。
その開いた壁の奥は、階段が下へ続いており、カビの匂いと、わずかに湿った、冷たい空気が漂ってきた。
「達也!」
大山が驚きに満ちた声をあげ、駆け寄ってきた。
「なんだ、この扉!」
「いや」達也は口元に笑みを浮かべた。「これは、水の流れが開けた扉だ。さあ、行くぞ。この下に、秘密がある」
達也は、未来の記憶を持たない大山を連れて、暗い地下へと続く階段を一歩踏み出した。
(続く)
時の音 -1
時の音 -2
時の音 -3
時の音 -4
時の音 -5
時の音 -6
時の音 -7
時の音 -8
時の音 -9
時の音 -10
時の音 -11
時の音 -12
時の音 -13
時の音 -14
時の音 -15
書籍サイトの紹介
Amazon 書籍
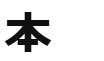
Amazon Kindle

音声で本を聞くAudible

