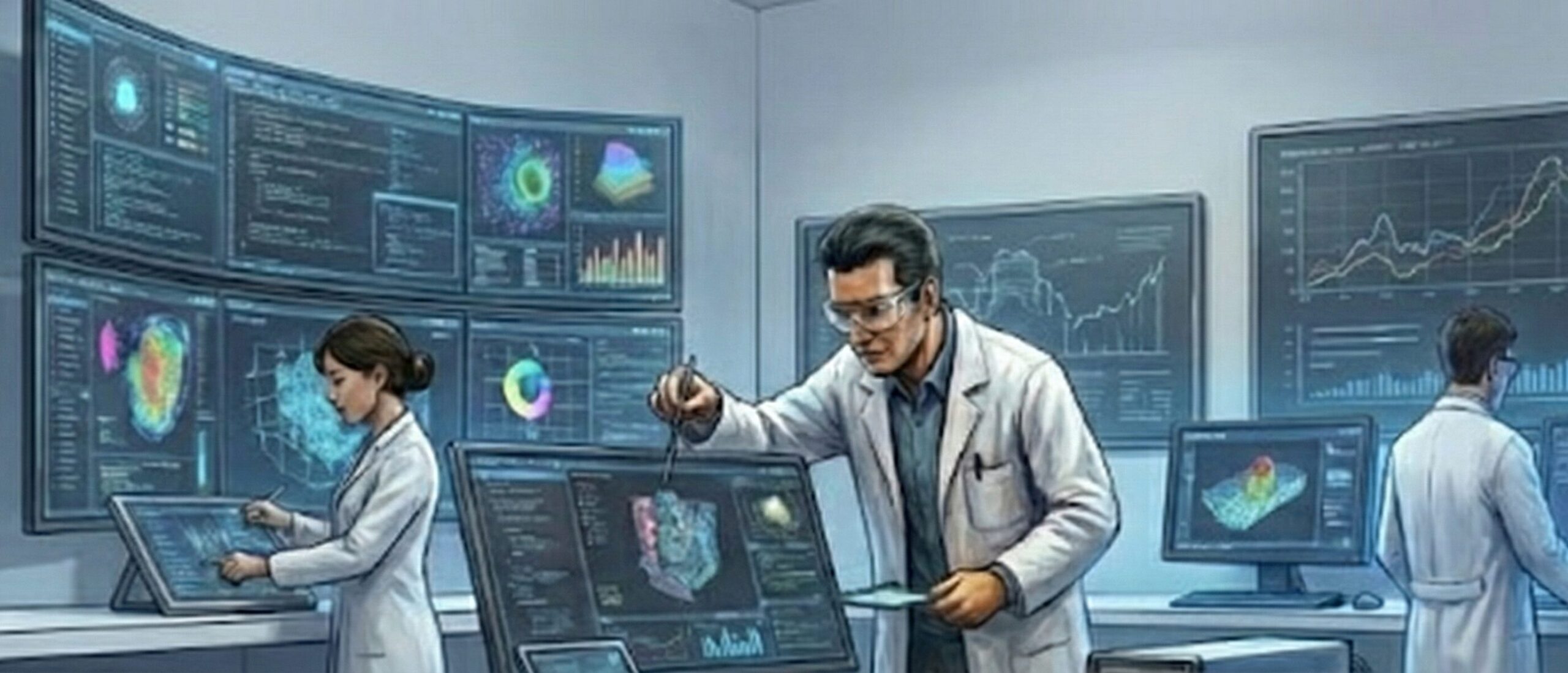第1話:プランク・スケールの暗号
哲也は思った。
「我思う、ゆえに我あり」
十七世紀のフランスの哲学者、ルネ・デカルトが暗いペチカのそばで一人辿り着いたその命題は、東京の摩天楼を見下ろすT大学理学部棟の最上階――重力と量子論の統合を目指す理論物理学の研究室においても、未だ揺るがない唯一の「確かなもの」として哲也の精神を繋ぎ止めていた。
窓ガラスを、二月の冷たく重い雨が執拗に打ち付けている。
眼下に広がる新宿から渋谷へと続く巨大な光の動脈は、まるで精緻に組み上げられたシリコンウェハー上の電子回路のようだった。数百万の人間が、それぞれの人生というアルゴリズムに従って、コンクリートとアスファルトの迷宮をせわしなく移動している。車のヘッドライト、明滅する巨大なネオンサイン、雨に濡れて黒光りする路面。
その圧倒的な「質量」と「リアリティ」。
誰もが疑うことのないこの堅牢な三次元の物理世界が、実は極薄の氷の上に描かれた脆弱な幻影に過ぎないのではないか。そんな狂気じみた疑念が、ここ数週間の哲也の脳髄から離れなかった。
事の始まりは、半年前。
南米チリ、標高5000メートルのアタカマ砂漠に建設された次世代の宇宙背景放射(CMB)観測網と、カミオカンデの系譜を継ぐ地下深部の巨大な重力波干渉計。世界最高峰の二つの独立した観測施設から送られてきた、ペタバイト級のデータ群の中に潜んでいた「わずかなノイズ」だった。
研究室の空気は、大型のサーバー群が吐き出す排熱ファンの低い唸り声と、すっかり酸化して酸っぱくなったコーヒーの匂いに支配されていた。
「だから、何度も言っているだろう。それはただの計器のキャリブレーション・エラーか、地殻の微小な熱揺らぎ(サーマルノイズ)だ」
背後で、ゲーミングチェアの軋む嫌な音がした。
同期の研究者である涼(りょう)が、苛立ちを隠せない声で吐き捨てた。涼は実証主義の塊のような男で、実験物理学の分野で若くして頭角を現している。彼にとって、観測機器のエラーバー(誤差範囲)に収まるような微小なデータのブレから、宇宙の根本法則をひっくり返すような突飛な仮説を立てる哲也の態度は、理論家の「悪い癖」にしか見えていなかった。
「キャリブレーション・エラーなら、なぜチリの望遠鏡と日本の地下干渉計という、全く原理も場所も異なる二つの施設で、小数点以下20桁目まで完全に一致するパターンのノイズが観測されるんだ?」
哲也は、充血した目でデュアルモニターの右側の画面を指差した。
そこには、宇宙の極小スケールにおける空間の「揺らぎ」を視覚化したグラフが表示されている。
「涼、アインシュタインの一般相対性理論を思い出してくれ。あの理論では、時空はどこまでも滑らかで連続的(アナログ)なファブリック(布)として記述されている。どんなに拡大しても、空間は滑らかに曲がるだけだ」
哲也はキーボードを叩き、一つの数式を画面の中央に呼び出した。
「プランク長だ」と涼が面倒くさそうに答えた。「メートル。物理学的に意味を持つ最小の長さの単位。それがどうした」
「このプランク長の極限スケールにおいて、空間はどうなっていると思う?」
哲也はグラフの縮尺を、限界まで拡大していった。滑らかな曲線を描いていたはずのグラフが、ある一定のスケールを超えた瞬間、突如としてギザギザの階段状のブロックへと変貌した。
「空間が……ちぎれている?」
涼が初めて、モニターに顔を近づけて眉をひそめた。
「ちぎれているんじゃない。空間は、そもそも連続体ではなかったんだ」
哲也の声には、恐怖にも似た熱が帯びていた。「空間は、これ以上分割できない『最小の体積』を持ったデジタルのピクセル(画素)の集合体だ。我々が滑らかな現実だと思っているこの世界は、極限まで拡大すれば、Minecraftのブロックのように不連続なモザイク状になっている。超弦理論やループ量子重力理論でも予言されていた『空間の離散化』が、ついに観測データとして現れたんだよ」
「待て、待て哲也。仮にそうだとしても、このノイズの形はおかしい」
涼の眼は、優秀な物理学者としての鋭さを取り戻していた。彼はグラフの階段状の歪みを指でなぞった。
「自然界の揺らぎ(ホワイトノイズ)なら、ガウス分布に従って完全にランダムになるはずだ。だがこの波形は……なんだ? 妙に規則的すぎる。まるで、意図的に特定の周波数帯だけがカットされているような……」
「そこに気づいたか」
哲也は深く息を吐き出し、もう一つのモニターに、全く別の幾何学的な模様を表示させた。それは物理学のデータではなく、情報科学の分野で使われる図だった。
「これは、GoogleやIBMが開発している量子コンピューターの『表面符号(サーフェス・コード)』のアルゴリズムだ」
哲也が静かに告げると、研究室の排熱ファンの音だけが、やけに大きく響いた。
「量子ビットは外部からのノイズに非常に弱く、すぐにエラーを起こして計算が破綻する。だから、複数の量子ビットを格子状に並べ、互いの状態を監視させて、エラーが起きた瞬間に隣接するビットがそれを検知して自動的に『修正』するプログラムを組む。それが量子誤り訂正符号だ」
哲也は、宇宙空間の揺らぎのデータと、量子誤り訂正符号のアルゴリズムの図を重ね合わせた。
二つの全く異なる分野のデータが、ピクセル単位で完璧な一致を見せた。
「……嘘だろ」
涼の口から、ひゅう、と空気が漏れた。
「嘘じゃない。我々の宇宙の根底にあるプランク・スケールの空間は、ランダムに揺らいでいるんじゃない。空間そのものが、何か膨大な情報の演算処理を行っており、そこで発生したバグ(エラー)を、システム自身が自動的に検知し、修正しているんだ」
哲也は椅子から立ち上がり、窓ガラスに歩み寄った。
冷たいガラスの向こう側では、相変わらず東京の街が圧倒的な光量で輝いている。
「涼。もしこの宇宙の最小単位が『情報(ビット)』であり、空間がエラーを自己修正する巨大なネットワークだとしたら。我々が『物質』だと信じているものや、リンゴを地面に落とす『重力』の正体は、一体何なんだ?」
自然界には存在し得ない、完璧にデザインされたアルゴリズム。
それが宇宙の基礎構造に組み込まれているという事実は、物理学の死を意味していた。我々は、神が作った美しい数式を探求していたのではなく、何者かが記述した「ソースコード」のリバース・エンジニアリングをさせられていただけだったのだ。
窓ガラスに映る自分の顔を、哲也はじっと見つめ返した。
この血肉も、脳内のシナプスを駆け巡る電気信号も、すべてがエラーを修正しながら走るプログラムの一部に過ぎないというのか。
ならば、今ここで「世界は偽物かもしれない」と疑い、恐怖しているこの『私』という存在の正体は、一体何なのだ?
「我思う、ゆえに……」
その先の言葉は、窓を叩く激しい雨音にかき消された。
すべてを疑い尽くすためのデカルトの刃は、物理学という絶対の盾を切り裂き、いよいよ哲也自身の「意識の在り処」へと迫ろうとしていた。