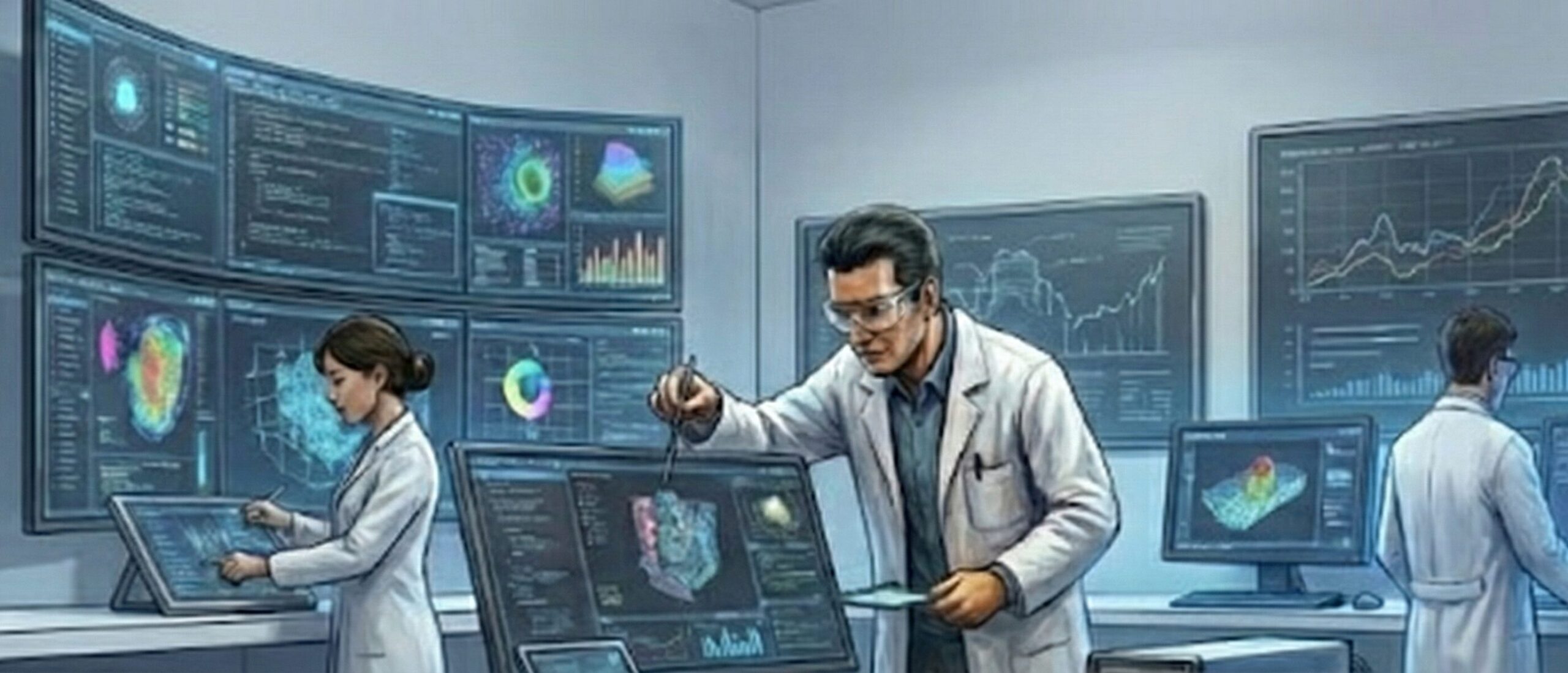第2話:エントロピーの亡霊と幻のリンゴ
T大学理学部棟の六階、もっとも日当たりの悪い北側の廊下の突き当たりに、その部屋はあった。
重厚な木製のドアを開けると、長年にわたって染み付いたパイプ煙草の甘く重い香りと、古紙が酸化する際特有のバニラに似た匂いが、哲也の鼻腔を突いた。壁の三面を覆い尽くす天井までの本棚には、アインシュタイン、ディラック、ファインマンといった物理学の巨人たちの原著論文が地層のように積み重なり、床には書き損じの計算用紙が雪のように散乱している。
部屋の主である老教授――白川(しらかわ)は、窓を背にして深い革張りの椅子に沈み込んでいた。
白川教授は、四十年にわたり「量子重力理論」の構築に生涯を捧げてきた、日本の理論物理学界における重鎮だ。アインシュタインが描いた『マクロな重力の時空』と、ミクロの世界を支配する『量子力学』。決して交わることのないこの二つの理論を統合する美しい方程式を見つけ出すこと。それが、彼の人生のすべてだった。
「……空間が、量子誤り訂正符号のアルゴリズムで構成されている、か」
白川教授は、哲也が持ち込んだ宇宙背景放射のノイズ解析データと、プランク・スケールにおける離散的な(不連続な)空間のグラフを拡大して、じっと見つめていた。
その声は、ひどく掠れていた。窓を打つ雨音にかき消されてしまいそうなほど、生命力に乏しい響きだった。
「はい」哲也は乾いた唾を飲み込んで頷いた。
「プランク長 のスケールにおいて、空間は滑らかな連続体ではありません。量子ビットの格子状のネットワークです。そして、我々が観測したこの規則的なノイズは、システムが宇宙空間の情報エラーを自己修正した『痕跡』だとしか思えないのです」
白川教授は、深く長い溜息をついた。
その溜息とともに、彼が四十年間信じ続けてきた強固な物理世界が、音を立てて崩れ去っていくのを哲也は感じた。
「哲也くん。君は、エリック・ヴァーリンデという物理学者が十数年前に提唱した仮説を覚えているかね?」
「……エントロピック重力仮説、ですか」
「そうだ」
教授は引き出しから、古びた一冊の革張りのノートを取り出した。それは彼が誰にも見せることのなかった、個人的な思索の核だった。ノートのページを開くと、そこには熱力学と情報理論の方程式がびっしりと書き込まれていた。
「リンゴはなぜ木から落ちるのか。ニュートンはそこに『万有引力』を見出し、アインシュタインは『質量が時空を歪めるからだ』と説明した。我々物理学者は皆、重力を宇宙の根源的な『基本相互作用(フォース)』だと信じて疑わなかった。だからこそ、重力を伝える素粒子――『重力子(グラビトン)』を探し求め、巨大な加速器を作り、数十年もの時間を無駄にしてきたのだ」
教授の言葉の端々に、血を吐くような後悔が滲んでいた。
「だが、もし君の言う通り、空間の正体が『情報ビットの集合体』だったとしたらどうなる?」
教授は立ち上がり、黒板の前に立った。チョークを握る彼の手は、小刻みに震えている。
「温度や圧力といったものが、ミクロな分子の運動の『統計的な平均値』に過ぎないように……重力もまた、根本的な力などではないのだ」
カツ、カツ、と乾いたチョークの音が部屋に響く。
「ゴムバンドを引っ張ると、元に戻ろうとする力が働く。あれはゴムの分子が引っ張り合っているわけではない。真っ直ぐに伸びた状態より、クシャクシャに丸まった状態のほうが『微視的な状態の数(情報量)』が多いからだ。自然界は常に、情報がより乱雑な状態――エントロピーが高い状態へと移行しようとする」
教授は黒板に、エントロピーの変化 と重力の関係式を書き殴った。
「物質が移動し、空間の情報(ビット)の配置が変わる。宇宙は、その情報量(エントロピー)を最大化しようと振る舞う。その結果として生じる熱力学的な錯覚……統計的に生み出される『見かけ上の引張力』。それこそが、我々が『重力』と呼んでいたものの正体なのだよ!」
チョークがポキリと折れ、床に転がった。
「重力子など、最初から存在しなかった。質量が時空を歪めるという相対性理論すら、マクロな視点から見た単なる『近似値』に過ぎなかったのだ」
教授は両手で顔を覆い、呻くように言った。
「私の四十年は……存在しない幻の素粒子を追いかけ、幻の方程式を組み立てていた、ただの道化だったということだ」
哲也は言葉を失った。
空間がデジタルな情報であるという哲也の観測結果は、皮肉にも、教授が最も恐れていた「重力の否定」を完璧に裏付けてしまったのだ。
「教授、それは違います。あなたの研究は無駄ではありません。あなたが積み上げた相対性理論の理解があったからこそ、私たちはこの真実に……」
「真実だと?」
教授が手を退け、哲也を睨みつけた。その眼はひどく充血し、底知れぬ恐怖に囚われていた。
「哲也くん、君はまだ自分が何を暴いてしまったのか分かっていない! もし空間が情報であり、重力すらただの演算結果の錯覚だとしたら、この宇宙のどこに『物質』が存在するというのだ?」
教授は自分の胸を強く叩いた。ドス、ドス、という鈍い音が響く。
「この肉体は? 脈打つ心臓は? 妻を愛し、君たち学生を育て、物理学に捧げた私のこの『人生』は! すべては極小の平面上で明滅する『0と1』のデータが、熱力学的な法則に従って勝手に書き換わっているだけの……ただの空虚なシミュレーションだと言うのか!」
それは、科学者としての絶望を通り越し、一人の人間としての存在意義(アイデンティティ)の完全な崩壊だった。
「……計算は合っている。君のデータは完璧だ。あまりにも、美しすぎる」
教授は力なく革張りの椅子に崩れ落ちた。彼の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ち、皺だらけの頬を伝った。
「だが教えてくれ、哲也くん。もしすべてがただの情報処理のプロセスだとしたら……今、私の頬を伝うこの涙の『温かさ』は、この胸を締め付ける『悲しみ』は、一体誰が、何のために演算しているというのだ?」
哲也は答えることができなかった。
排熱ファンの唸り声と、窓を叩く雨音だけが、答えのない部屋に虚しく響き続けている。
その日を最後に、白川教授は大学から姿を消した。彼のデスクには、冷え切ったコーヒーと、開かれたままの革張りのノートだけが残されていた。
哲也は思った。
「我思う、ゆえに我あり」
恩師を絶望の淵へと突き落としたこの冷酷な宇宙のソースコードの中で。
我々が「私」という意識を持ち、涙を流し、苦悩する理由。それこそが、この張りボテの宇宙に仕掛けられた最大のバグであり、同時にシステムを紐解く最後の鍵(マスターキー)なのだと。哲也は暗闇の中で、静かに決意を固めていた。