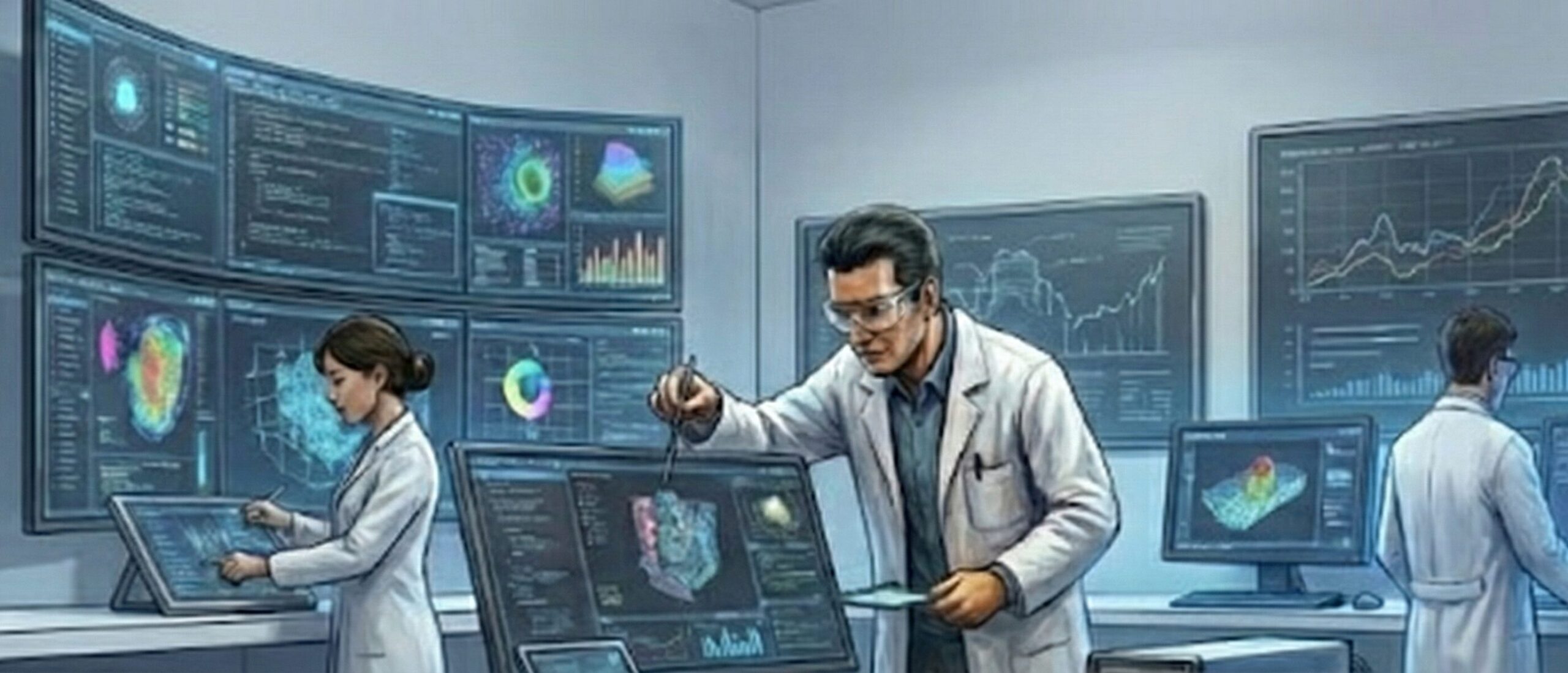第3話:二次元の牢獄と、体温の証明
T大学理学部棟の六階。主を失った白川教授の研究室は、死んだ巨獣の胎内のように冷たく、静まり返っていた。
窓を打ち付ける冷雨は四日目に入り、東京の街を灰色のノイズで塗り潰している。
哲也は、デスクの真ん中に取り残された教授の革張りのノートを見つめていた。表紙の擦り切れた黒い革は、長年教授の指先から滲み出た脂と汗を吸い込み、鈍い光を放っている。この中には、一人の偉大な物理学者の精神を完全に破壊した「毒」が封印されている。
哲也は震える指先で、ノートのページをめくった。
エントロピック重力――重力が幻であるという証明のページを越えると、そこには黒々とした万年筆のインクで、巨大なブラックホールに関する一つの方程式が書き殴られていた。
「ベッケンシュタイン・ホーキングの公式……」
哲也の口から、掠れた声が漏れた。
それは、ブラックホールが持つ情報量(エントロピー )を算出するための、現代物理学の金字塔とも言える数式だ。はボルツマン定数、cは光速、Gは重力定数、 はプランク定数。
だが、この数式には、古典物理学の常識を根底から覆す、ある「致命的な異常」が潜んでいる。
通常、ある空間の中に詰め込める情報量は、その空間の『体積(Volume)』に比例する。箱が大きければ大きいほど、多くの物を入れられるのは自明の理だ。
しかし、この公式において、ブラックホールの情報量Sは、体積ではなく『表面積 A(Area)』に完全に比例しているのだ。
ノートの余白には、教授の乱れた筆跡でこう記されていた。
『空間の最大情報量が、三次元の体積ではなく、二次元の表面積によって上限を決定される。それはすなわち、この宇宙の本質的な自由度が「二次元」であることを意味している。我々が認識している奥行き(Z軸)は、数学的に存在しない』
哲也は息を呑んだ。
マルダセーナが提唱した「AdS/CFT対応(反ド・ジッター空間/共形場理論対応)」。ノートの後半は、その複雑極まりないテンソル計算の羅列で埋め尽くされていた。
重力が存在する五次元のバルク(内部空間)の物理法則は、重力が存在しない四次元の境界(表面)の量子力学と、数学的に「完全に等価」であるという証明。次元を一つ落としても、情報が一切失われないという絶対的な数学的真理。
「ホログラフィック原理……」
哲也は後ずさり、本棚に背中を打ち付けた。
空間が存在しないだけではない。この宇宙は、果てしなく遠い「二次元の境界面」に張り付いた量子ビット(0と1の情報)が、互いに量子もつれ(エンタングルメント)を起こすことで生み出されている、巨大なホログラム(投影)に過ぎなかったのだ。
木から落ちるリンゴも、地球を回る月も、窓ガラスを叩く雨だれも。そして今、恐怖に震えている哲也の心臓、肺、血液のすべてが。
遥か彼方の極小の平面上で明滅するデータが、三次元の立体映像として「映し出されている」だけの幻影。我々は、映画館のスクリーンの上に描かれた登場人物でありながら、自分たちを立体的で血肉の通った存在だと錯覚しているだけのデータ処理の残像なのだ。
「……何を見ている、哲也」
背後から、低く刺々しい声が響いた。
振り返ると、ずぶ濡れのスーツ姿の涼(りょう)が立っていた。彼の顔は疲労で青ざめ、白川教授の失踪による焦燥感で眼は血走っていた。
「涼。教授は……真理に辿り着いたんだ。このノートを見てくれ」
哲也はノートを差し出そうとしたが、涼はそれを乱暴に払い除けた。重いノートが床に落ち、バサリと不吉な音を立てる。
「数式のお遊びはもういい! 教授はどこだ! 自分がただの二次元データの影法師だと知って、絶望して海にでも身を投げたとでも言うのか!」
涼の怒号が、埃っぽい部屋の空気を震わせた。実証主義の塊である彼は、自分の目の前にある「物質」のリアリティを手放すことができず、必死に抵抗していた。
「現実を見ろ、哲也! 俺が今、お前の胸ぐらを掴んでいるこの『力』は幻か? お前の手首で脈打っているその『鼓動』はデータか? 俺たちは血を流し、飯を食い、細胞を分裂させて生きているんだぞ!」
涼は哲也の胸ぐらを掴み上げて怒鳴ったが、その手は小刻みに震え、やがて力なく離された。
優秀な物理学者である涼には、分かってしまっていたのだ。床に落ちたノートの数式に、たった一つの論理的な破綻も存在しないことが。
「なぁ、哲也……」涼の声は、迷子になった子供のように震えていた。「もし教授の言う通り、すべてが二次元の情報の投影だとしたら。俺たちが論文を書いて『喜ぶ』ことも、教授が消えて『悲しい』と泣くことも、あらかじめ境界面に記述されたデータ処理のプロセスに過ぎないってことか?」
哲也は答えることができなかった。
無言のまま研究室を飛び出し、気がつけば、土砂降りの渋谷スクランブル交差点に立っていた。
傘の波が、信号の青とともに一斉にうごめく。数千人の人間が交差するその光景は、圧倒的な情報量の塊だ。
(この人波も、雨の冷たさも、ビルを叩く風の音も。すべてがスクリーンに映し出された二次元データの投影なのか?)
「哲也!」
人混みの中から、赤い傘を傾けて駆け寄ってくる人影があった。大学で哲学を専攻する幼馴染の佳奈(かな)だった。彼女は哲也のずぶ濡れで青ざめた顔を見るなり、傘を投げ捨ててその腕を強く掴んだ。
「どうしたの? 教授が失踪したって聞いたわ。まるで幽霊でも見るような目で……この世界を見てるわよ」
近くの静かな喫茶店に入り、温かいダージリンティーを前にしても、哲也の震えは止まらなかった。彼は、自分が辿り着きつつある恐ろしい真実の片鱗を彼女に語った。
宇宙が二次元のホログラムであり、自分たちの肉体も感情も、情報データの投影に過ぎないということを。
「……だから、僕らのこの絶望も、君のその温かい手も、あらかじめ決定された数式通りの物理現象……いや、ただのデータ処理なんだ。悲しいという感情すら、プログラムのエラー出力に過ぎない」
佳奈はしばらく黙って紅茶の湯気を見つめていた。カチャリとカップをソーサーに置く音が、やけに鮮明に響いた。
彼女は静かに、しかしはっきりと首を振った。
「私は物理学の数式は分からないわ。でもね、哲也。もしこの世界が誰かの作った精巧なシミュレーションだとしても……」
佳奈はテーブル越しに身を乗り出し、哲也の冷え切った両手を、自分の両手でしっかりと包み込んだ。
「私が今、あなたを心配して胸が痛むこの感情や、あなたを温めたいと思うこの『体温』は、絶対に本物よ」
手のひらから伝わる、生々しいほどの熱。
「痛い、悲しい、愛おしい。その感覚だけは、どんな数式でも否定できないわ。デカルトだってそう言ったんでしょう? すべての物質を疑い尽くしても、疑っている『自分自身の意識』だけはどうしても消せないって」
その温もりが、哲也の脳裏に稲妻のような閃きをもたらした。
(そうだ。もしすべてが二次元の境界面での情報演算プロセスに過ぎないのなら……なぜ、この宇宙というシステムには「意識(私)」が存在するんだ?)
単なるデータ処理ならば、暗闇の中で無意識のまま演算を続ければいい。登場人物にわざわざ「世界を感じさせる」必要などない。なぜシステムは、わざわざ「自己を認識し、体温を感じる観測者」を構築したのか。
「佳奈……」
哲也は、彼女の手を握り返した。
それは、哲学の問いではない。宇宙の「システム要件」に関わる、物理学の最も深い謎(バグ)への入り口だった。
我思う、ゆえに我あり。
十七世紀の哲学者が到達した言葉は、哲学などではなかった。それはこの宇宙のソースコードに隠された、絶対的なシステム要件のヒントだったのだ。