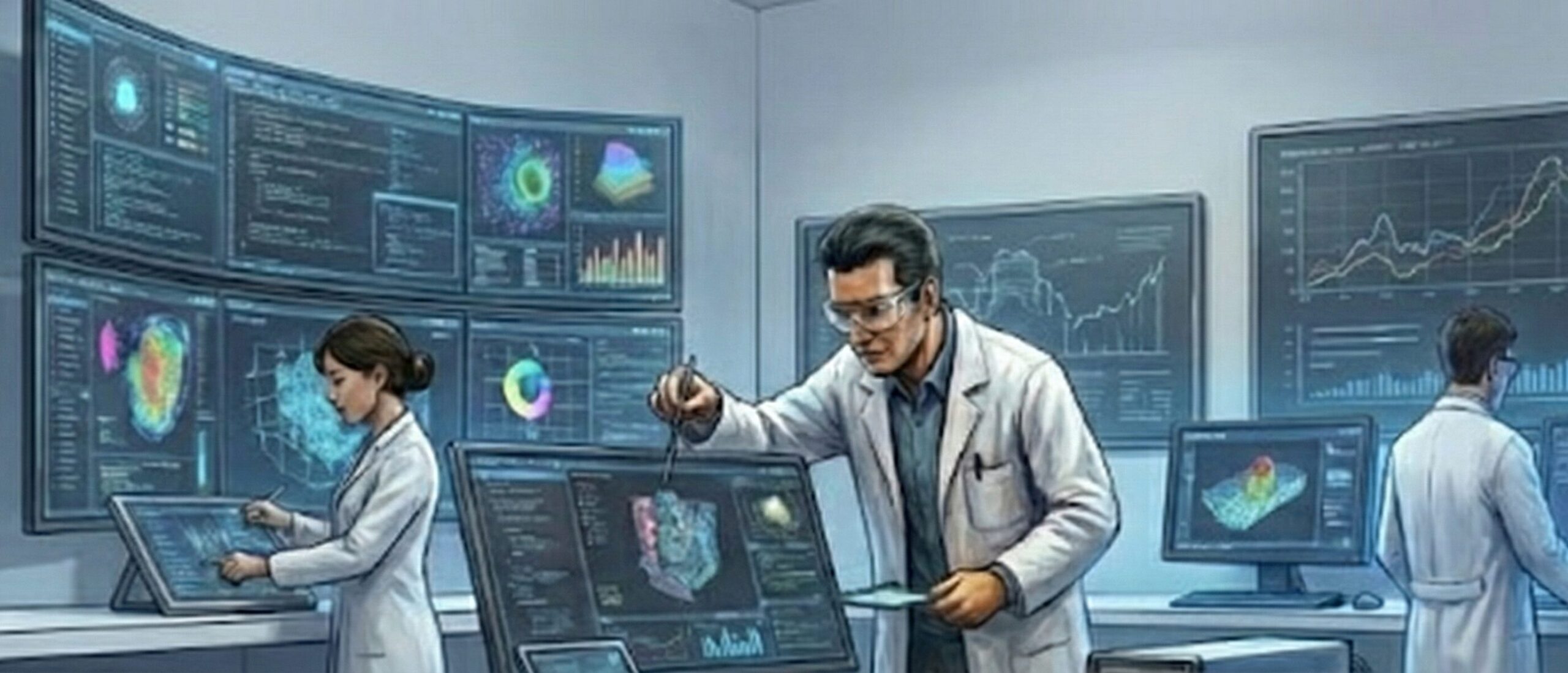第4話:絶対速度と宇宙のクロック周波数
佳奈の小さな手から伝わった生々しいほどの熱は、冷え切った哲也の精神に、ある種の「特異点」として焼き付いていた。
土砂降りの渋谷からT大学の研究室に戻った哲也は、濡れたコートを脱ぐのも忘れ、暗闇の中でホワイトボードの前に立っていた。
窓の外では、東京の夜景が雨に滲んで、無数の光のピクセルとなって明滅している。
「意識、体温、感情……」
哲也はマーカーを握りしめ、ホワイトボードの端にその言葉を書き込んだ。
もしこの世界が、二次元の境界面に張り付いた量子ビットが織りなす「ホログラム(投影)」に過ぎないのなら。我々の肉体も、脳細胞も、シナプス間を走る電気信号すらも、極小の平面上で実行されているデータ処理の残像だ。
だが、その処理結果を「熱い」と感じ、「悲しい」と認識する『私(観測者)』の存在だけは、情報の投影という論理だけではどうしても説明がつかない。
システムは、なぜ観測者を必要としたのか。
「おい、哲也。いつまでそこに突っ立っている」
背後から、ひどく疲労した声が響いた。デスクの影から顔を上げたのは、涼(りょう)だった。彼は白川教授の失踪以来、ろくに睡眠も取らず、警察への連絡や大学側との対応、そして教授の残したPCの暗号化されたログの解析に追われていた。
「教授のIDカードの履歴を調べたが、三日前の深夜に理学部棟を出たきり、足取りは完全に途絶えている。監視カメラにも映っていない」
涼は充血した目をこすりながら、力なく首を振った。
「……なぁ、哲也。お前が言った『宇宙は二次元のデータだ』って話。もしそれが本当なら、教授は自らの意思で消えたんじゃない。世界の真実に気づいたバグとして、システムから『デリート(削除)』された……なんて、ことじゃないだろうな?」
涼の言葉は、冗談の形をとってはいたが、その声の震えは彼自身がその可能性に怯えていることを如実に物語っていた。
「……バグ、か」
哲也はホワイトボードから向き直り、涼の疲れ切った顔を見つめた。
「涼。教授のノートが証明したホログラフィック原理は、空間が幻であることを暴いた。だが、もう一つ、僕たちが日常的に受け入れている『幻』がある。アインシュタインの相対性理論だ」
「相対性理論? それがどうした。あれは現代物理学の最も強固な基盤だぞ」
「相対性理論の根本的な大前提は何か。それは『光の速度()は、どんな観測者から見ても常に一定である』という光速度不変の原理だ」
哲也はホワイトボードの中央に、大きく数式を書き殴った。
「秒速約30万キロメートル。光は宇宙で最も速く、これを超える速度で情報を伝達することは絶対にできない。アインシュタインはこれを『宇宙の絶対的な制限速度』として理論を組み立てた。だが……なぜだ?」
カツン、とマーカーで盤面を叩く音が、静まり返った研究室に響いた。
「なぜ、光の速度は無限大じゃない? なぜ、『299,792,458』などという中途半端な数字で頭打ちになるんだ? 物理学者は一世紀以上、これを『そういうものだから』と受け入れてきた。だが、宇宙がホログラム(シミュレーション)であるという前提に立てば、この数字の本当の意味は小学生でも分かる」
哲也の眼に、狂気にも似た鋭い光が宿った。
「光速()は、移動速度の限界じゃない。この宇宙を演算している量子コンピューターの『最大クロック周波数(処理速度の限界)』なんだよ」
涼の呼吸がピタリと止まった。排熱ファンの唸り声だけが、二人の間を埋めている。
「……クロック周波数だと?」
「そうだ。パソコンのCPUと同じだ。システムが1秒間に処理できる情報量には、ハードウェア的な限界がある。宇宙という巨大なシミュレーターが、四次元時空(三次元空間+時間)をレンダリングする際の、最大の更新速度。それが秒速30万キロメートルという数値として、僕たちの世界に現れているだけなんだ」
哲也はホワイトボードに、特殊相対性理論において最も有名な「時間の遅れ(タイム・ディレーション)」を示すローレンツ変換の式を書き連ねた。
「運動する物体の速度()が光速()に近づくほど、その物体の流れる時間()は遅くなる。これは観測事実だ」
哲也は、速度 と光速 の項を丸で囲んだ。
「これまでは『速度が上がると、空間と時間が歪むからだ』と説明されてきた。だが、情報科学の視点で見れば全く違う。物体がシステム内で高速移動するということは、背景の空間座標を猛烈な勢いで書き換える『高負荷な演算』をシステムに要求するということだ」
涼の顔から、みるみると血の気が引いていく。実証主義の実験物理学者である彼の脳内で、相対性理論とコンピューター・サイエンスが、最悪の形で結びつき始めていた。
「まさか……ラグ(遅延)だとでも言うのか?」
涼の声は掠れていた。
「その通りだ」
哲也は冷酷な真理を、無慈悲に宣告した。
「移動という座標更新の演算に、宇宙の処理能力(リソース)が割かれすぎる。するとシステムは、その物体に対する『時間(ローカルの更新頻度)』の割り当てを減らして、フリーズを回避しようとする。それが、光速に近づくと時間が遅れるという現象の正体だ。我々が『相対性理論』と呼んで崇めてきた美しい数式は……単なる『演算の遅延(ラグ)をごまかすための、システム側の負荷分散アルゴリズム』に過ぎなかったんだ」
「馬鹿な……っ!」
涼は弾かれたように立ち上がり、椅子を蹴り倒した。
「じゃあ、重力が強い場所で時間が遅れる一般相対性理論はどうなる! ブラックホールの周囲では時間が止まるんだぞ!」
「同じことだ。ブラックホールは、無限大の情報(エントロピー)が極小の領域に圧縮された状態だ。それを演算しようとすれば、システムは完全にパンクする。だからブラックホールの事象の地平面では、システムが処理を放棄し、時間が完全に『フリーズ』して止まるんだ」
アインシュタインが見出した宇宙の美しさ。
それが、ただの「コンピューターの処理落ち」の法則に過ぎなかったという事実。
「ハッ……ハハハ……」
涼の口から、乾いた笑いが漏れた。両手で顔を覆い、狂ったように笑い続ける。
「相対性理論が、PCのラグの法則……? アインシュタインは、バグの報告書を書いてノーベル賞をもらったのか? 俺たちのこの百年間の物理学は、ただのゲームの不具合(グリッチ)の研究だったって言うのかよ!」
崩れ落ちる涼を見下ろしながら、哲也の胸には重い鉛のような絶望が居座っていた。
空間は、二次元の投影。
重力は、情報の熱力学的な錯覚。
そして時間と光の速度は、システムのクロック周波数と演算ラグ。
この宇宙を構成する物理法則のすべてが、「完全なシミュレーションである」というたった一つの前提で、恐ろしいほど完璧に説明がついてしまう。白川教授が失踪した理由が、今なら痛いほどよく分かった。この真理は、人間の精神を内側から食い破る猛毒だ。
だが、哲也は佳奈のあの「手の温もり」を思い出していた。
すべてが完璧な演算(プログラム)ならば。
なぜ、このシステムには「それ(時間や空間の歪み)を観測し、苦悩する『私』」が必要なのか。
宇宙が計算リソースを節約するために相対性理論という遅延アルゴリズムまで用意しているのなら、なぜわざわざ「自己意識」という、最も演算負荷の高く、非効率的なバグを放置しているのか。
「我思う、ゆえに我あり……」
哲也の呟きは、雨音に掻き消された。
彼はまだ知らなかった。この「意識」の謎を追うことが、宇宙を統べる巨大なシステムからの、直接的な『介入』と『排除(ガベージコレクション)』を招く引き金になることを。
窓の外の東京のネオンが、まるで電圧が落ちたように、ほんの一瞬、不自然に明滅した。