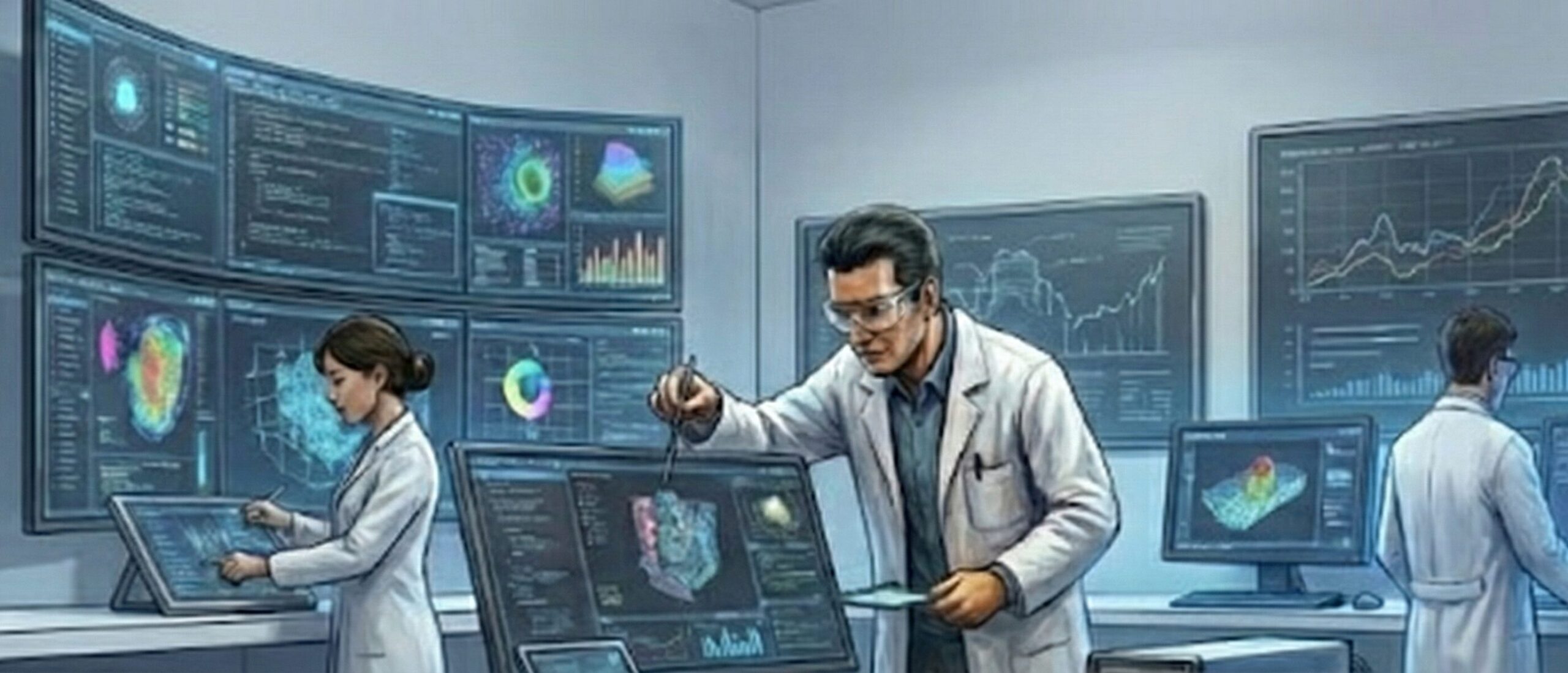第5話:渋谷、描画遅延(レンダリング・ラグ)(5/30)
深夜のT大学理学部棟。白川教授の部屋の空気は、物理学の死を告げる通夜のように重く淀んでいた。
「……相対性理論が、処理遅れの法則……?」
涼(りょう)は、床に崩れ落ちたまま、壊れたレコードのように同じ言葉を繰り返していた。 実験物理学者として、彼が信じてきた堅牢な宇宙。加速器の中で光速近くまで加速された粒子が示す寿命の延び、GPS衛星が毎日行っている時間の補正。それら全ての輝かしい「実証データ」が、今や巨大な計算機のスペック不足を隠蔽するための、言い訳(ワークアラウンド)になってしまった。
「立てよ、涼」 哲也は、魂の抜けた友人の腕を掴み、無理やり引き立たせた。 「ここにいたら気が狂う。外の空気を吸うんだ」
二人は、逃げるように研究室を後にした。 エレベーターが下降する間も、涼はうわ言のように呟き続けていた。 「重力は幻、時間はラグ、俺たちは二次元の影……。じゃあ、今俺が感じているこの吐き気はなんだ? この絶望的な疲労感は、どの座標のデータがバグった結果なんだよ……」
哲也は無言で唇を噛んだ。 その問いこそが、この完璧な虚構監獄に残された最後の扉なのだ。だが、今の涼にそれを説くことは、溺れる者に重りを渡すに等しい。
外に出ると、東京はまだ激しい雨に晒されていた。 時刻は午前一時を回っているが、渋谷の街は眠ることを知らない。傘の花が開いたスクランブル交差点。ビル壁面の巨大ビジョンが放つ極彩色の光。車のテールランプが濡れたアスファルトに赤い川を描き、無数の騒音が混じり合って一つの巨大な唸り声を上げている。
圧倒的な情報量(エントロピー)の奔流。 つい数日前まで、哲也はこの光景を「現実のエネルギー」として感じていた。だが今は違う。
(遅い……)
哲也の変質した知覚は、この世界の「フレームレート」を意識し始めていた。 行き交う人々、走るタクシー、舞い落ちる雨粒。それら全ての動きが、極めて精巧ではあるが、どこかカクついた、不連続なコマ送りの映像に見えてくる。
脳が、世界の認識方法を書き換えてしまったのだ。 一度「これはゲーム画面だ」と認識してしまえば、今まで気にならなかったテクスチャの粗や、ポリゴンの継ぎ目ばかりが目についてしまうように。哲也の眼は、無意識のうちにこの世界の「計算の粗(あら)」を探し始めていた。
そして、それは唐突に訪れた。
「……え?」
最初に気づいたのは、隣を歩いていた涼だった。 スクランブル交差点の信号が赤に変わり、歩行者たちが足を止めた瞬間。
キィィィン、という耳障りなハウリングのような音が、交差点のスピーカーから響いた。 普段なら「通りゃんせ」や鳥の鳴き声が流れるはずの、視覚障害者用の誘導音だ。それが、壊れたオーディオファイルのように、不快な高音の断片だけを高速でループ再生し始めたのだ。
『ピョ、ピョ、ピョ、ピョ、ピョ、ピョ――――』
周囲の雑踏が一瞬、訝しげにスピーカーを見上げる。だが、ほとんどの人間は「故障か」と気にも留めずに再びスマホに目を落とす。 だが、物理学者である二人は違った。
「おい、哲也……今の音……」 涼の顔色が、青ざめるのを通り越して土気色になった。 「スピーカーの故障じゃない。空気が……振動していなかった」
「な、何を言ってる?」
「俺は音響工学もやってたんだぞ! スピーカーの膜が物理的に振動して空気を震わせれば、音波には必ず特定の減衰パターンが生まれる。だが今の音は、空気を介さずに、俺の鼓膜の神経データに直接『書き込まれた』ような、デジタルな違和感があった!」
涼の言葉に、哲也の背筋が凍りついた。 もしこの世界がシミュレーションなら、我々の五感もまた、脳というデバイスに入力される電気信号のパラメータに過ぎない。システムが「音」の物理演算を省略し、結果だけを直接入力したとしたら?
「涼、落ち着け。きっと雨で回路がショートしただけだ」 哲也は努めて冷静な声を出し、涼の肩を抱いて歩き出した。だが、哲也自身の心臓は早鐘のように打ち鳴らされていた。
(まさか、俺たちが『気づいた』からか?)
ホログラフィック原理、光速の正体。 彼らが研究室で暴いた宇宙のソースコード。それによって、彼らという「観測者」のパラメータが、システム側から見て危険な閾値(しきいち)を超えてしまったのではないか。
「あ、あれ……見て……」
交差点を渡りきり、センター街に入ろうとした時、今度は涼が立ち止まり、空を指差して絶句した。
「なんだよ、今度は……」 哲也が苛立ちながら見上げた先。そこには、物理学者としての理性を根底から破壊する光景が広がっていた。
雨が、止まっていた。
いや、正確には違う。 空から降り注ぐ無数の雨粒のうち、センター街の入り口付近にある、直径五メートルほどの局所的な空間の雨粒だけが、空中で完全に静止していたのだ。
まるで、そこだけ時間が凍りついたように。 あるいは――処理落ちしたビデオゲームのように。
「な、なんだあれ……重力が、仕事をしていない……?」 涼が後ずさり、ガードレールにぶつかった。周囲の通行人は、傘をさして足早に通り過ぎていく。奇妙なことに、誰もこの異常な光景に気づいていないようだった。
(認識阻害……?)
哲也は戦慄した。 システムが、特定の領域の物理演算(雨の落下シミュレーション)を一時停止させている。それだけではない。その「バグ」を、周囲のモブ(他の人間)に認識させないよう、彼らの視覚情報にリアルタイムでパッチを当てているのだとしたら。
だが、哲也と涼には「見えて」しまっている。
「……バグだ」 哲也の口から、乾いた声が漏れた。 「涼、見ろ。あれが教授が恐れた世界の真実だ。この領域の計算負荷が高すぎて、システムが雨の物理演算を後回しにしたんだ!」
「やめろ! そんなことあるわけがない! 質量保存の法則は!? 運動量保存は!?」 涼は半狂乱で叫んだ。彼が信じてきた物理法則が、目の前でシステムの都合によってレイプされている。
その瞬間。 静止していた数千の雨粒が、一斉に「再起動」した。
バシャァァァン!!
溜まっていた数秒分の雨水が、巨大な水の塊となって一度に地面に叩きつけられた。アスファルトが悲鳴を上げ、周囲の通行人が驚いて飛び退く。
「きゃあ!?」 「なんだ!? ゲリラ豪雨か!?」
人々はパニックになりかけたが、すぐに何事もなかったかのように、再びそれぞれの目的地へと歩き始めた。彼らの認識の中では、今の現象は「ちょっと変な雨の降り方」として自動的に補正されてしまったのだ。
だが、哲也と涼は動けなかった。 ずぶ濡れのまま、互いの顔を見合わせる。
「……始まったんだ」 哲也は確信した。冷たい雨が骨まで染み込んでくるが、その寒さとは別の種類の悪寒が全身を走った。
「俺たちが『気づいた』せいで、この領域の監視レベルが上がった。その負荷に、システムが耐えきれなくなってきている」
ここは、もはや安全な研究室ではない。 彼らが暴いた真実は、ただの理論ではなくなった。 東京というこの巨大な仮想空間そのものが、異物を検知した免疫システムのように、彼らに牙を剥き始めたのだ。
ビルの壁面に設置された巨大な街頭ビジョンが、突然、ノイズを発して明滅した。 映し出されていたアイドルの笑顔が歪み、一瞬だけ、真っ黒な背景に、人間には理解不能な白い文字列のエラーコードが羅列されたのを、哲也は見逃さなかった。
[Warning: Local reality rendering latency exceeded threshold. Observers ID: T-998, R-401 detected.] (警告:局所現実のレンダリング遅延が閾値を超過。観測者ID T-998, R-401を検知)