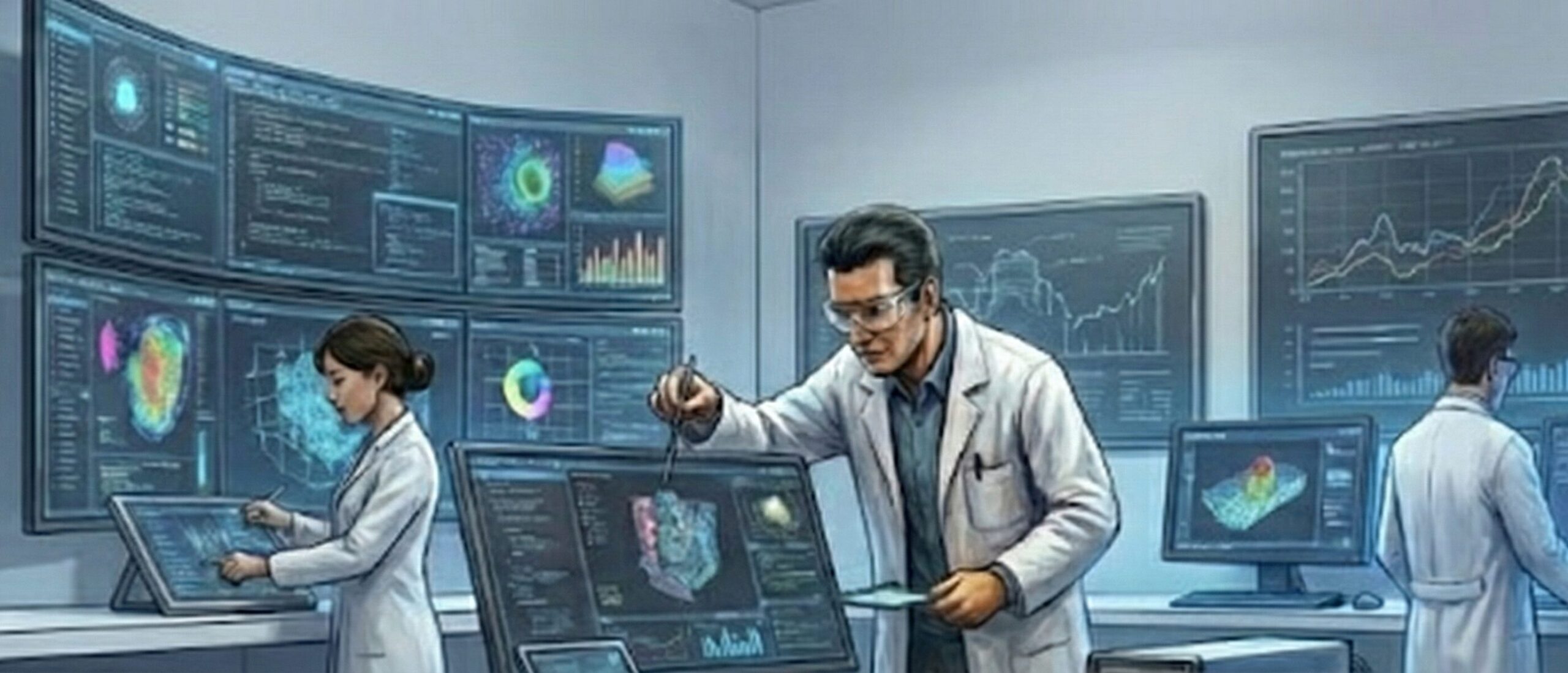第6話:ガベージコレクション
巨大な街頭ビジョンに一瞬だけ走った白い文字列。
[Warning: Local reality rendering latency exceeded threshold. Observers ID: T-998, R-401 detected.]
哲也の網膜に焼き付いたそのエラーコードは、瞬きをした次の瞬間には、再び薄っぺらなアイドルの作り笑いへと上書きされていた。 だが、システムの「目」が完全に自分たちを捉えたという悪寒は、雨に濡れた衣服よりも冷たく哲也の心臓を鷲掴みにしていた。
「涼、ここから離れるぞ。早く!」
哲也は、濡れたアスファルトにへたり込みそうになっている涼の腕を強く引いた。 「離れるって……どこへ行くんだよ! 物理法則が狂ってるんだぞ! どこへ逃げたって、この宇宙(システム)の内側じゃないか!」
涼の叫び声は、雨音と渋谷の喧騒にかき消されそうだったが、その声帯の震えには、実験物理学者としての理性が完全に崩壊しつつある悲鳴が混じっていた。 彼が三十年間信じ、観測し、数式で証明してきた「絶対的な現実」が、今や安っぽいゲーム機の処理落ちのように目の前でボロボロと剥がれ落ちているのだ。精神が耐えられるはずがなかった。
「いいから立て! ここは情報量が多すぎる。システムの監視(レンダリング)が集中してるんだ!」
哲也は強引に涼を引きずり起こし、センター街のメインストリートから外れ、薄暗い路地裏へと駆け込んだ。 ネオンの光が届かない、ゴミ袋が積み上げられた狭い路地。換気扇から吐き出される油の匂いと、ネズミが這い回る気配。普段なら顔をしかめるようなその「猥雑なリアリティ」すら、今の哲也にはシステムが生成した『環境テクスチャ』にしか見えなかった。
息を切らしながら立ち止まると、涼がレンガ調の壁に手をついて激しく嘔吐した。 胃液がアスファルトにぶちまけられる。
「ハァ……ハァ……哲也……俺は狂ったのか? それとも、世界が狂ったのか?」 口元を拭いながら、涼は焦点の合わない目で哲也を見た。
「狂ってなんかいない。僕たちはただ、管理者権限のないファイル(真理)にアクセスしてしまっただけだ」 哲也は周囲を警戒しながら答えた。
その時だった。 路地裏の入り口を通り過ぎていく「通行人たち」の挙動に、哲也は強烈な違和感を覚えた。
傘をさした数人のサラリーマン、若者のグループ、カップル。 彼らの歩幅。腕の振り方。地面を蹴るタイミング。 それらが、恐ろしいほど「完全に一致」していたのだ。
カツ、カツ、カツ。 全く同じリズムで、全く同じモーションデータ(アニメーション)を再生するように、無表情の人間たちが路地の入り口を横切っていく。
「おい……見ろよ、あれ……」 吐き気を催していた涼もそれに気づき、息を呑んだ。 「コピー・アンド・ペーストだ。計算負荷を下げるために、モブ(通行人)の行動アルゴリズムとモーションデータを使い回しやがった……!」
涼の震える声が、路地に響く。 システムが、哲也と涼という「高負荷なエラー処理(観測者)」にリソースを割くため、周囲の背景となる人間たちの演算を極限まで省略(サボって)しているのだ。 彼らにはもはや、個別の人生も、今日帰るべき家を思う感情も与えられていない。ただ背景を埋めるための、同期したポリゴンの塊でしかなかった。
「……来るぞ」 哲也が低く呻いた。
路地の奥。積み上げられたゴミ袋のさらに向こう側の空間が、不自然に「歪んだ」。 光が屈折しているのではない。空間を構成するピクセルの座標データそのものが、ごっそりと欠落したのだ。
モザイク状に崩れた空間の穴から、真っ黒な「無」が露出した。 光すら反射しない、絶対的な暗黒。そこから、人間の輪郭だけを粗くトレースしたような、のっぺらぼうの影が這い出してきた。
「な、なんだあれは……!」 涼が後ずさりする。
「ガベージコレクタ(不要メモリの破棄プログラム)だ」 哲也の頭脳は、恐怖を通り越して異常なほど冷徹に回転していた。 「僕たちというバグを、システムからデリート(削除)しに来たんだ」
黒い影は、重力や慣性の法則を完全に無視していた。 歩くという物理的なプロセスを踏まず、コマ送りのように「座標をスキップ」して、音もなく二人に接近してくる。影が通過した跡の壁や地面は、テクスチャが剥がれ落ち、ワイヤーフレーム(線の骨組み)だけが剥き出しになっていた。
「逃げるぞ、涼!!」
哲也の叫びとともに、二人は路地裏を逆方向へと駆け出した。 だが、摩擦係数を失い始めた路面は氷のように滑り、涼が大きくバランスを崩して転倒した。
「ぐあっ……!」 「涼!」
哲也が振り返った瞬間、黒い影はすでに涼の数メートル背後まで迫っていた。 影がノイズにまみれた腕を振り上げる。あれに触れられれば、涼を構成するすべての量子データは「不要な変数」として初期化され、宇宙から完全に抹消される。
「くそっ、来るな! 俺はここにいる! 俺は質量を持った人間だ!!」 涼はパニックになりながら、足元に落ちていた空のビール瓶を影に向かって力任せに投げつけた。
物理学者が放った、渾身の質量弾。 だが、放物線を描いて飛んだビール瓶は、影に命中する直前で『存在しなかったこと』にされた。割れる音すらせず、空中でフッとポリゴンの塵となって消滅したのだ。
「ヒィッ……!」 涼の顔から、最後の希望が消え失せた。運動量保存の法則が、目の前で書き換えられたのだ。彼を守る物理学の盾は、もはや紙切れ以下の意味しか持たなかった。
影の腕が、涼の肩に触れようとしたその刹那。
「我思う、ゆえに我あり(I think, therefore I am)!!」
哲也の咆哮が、路地裏に轟いた。 彼は涼の前に立ちはだかり、迫り来る黒い影を正面から、血走った眼で強烈に「睨みつけた(観測した)」。
(俺はここにいる! 俺の意識は、システムの外側にある真実だ! この空間の座標を、俺の観測で上書きしてやる!)
哲也の脳内で、佳奈のあの「温かい手」の記憶がフラッシュバックした。 痛い、悲しい、熱い。その強烈な主観的リアリティ(自我)。 システムが最も演算負荷を強いられ、なおかつ排除しきれない「意識」という名の最大のバグ。
哲也が強烈な意志を持って空間を「観測」した瞬間。 バチィィィン!! という青白いスパークとともに、路地裏の空間が強引に再レンダリング(再描画)された。
剥き出しになっていたワイヤーフレームが再びレンガのテクスチャを取り戻し、摩擦係数が復活する。 そして、システムが用意した排除プログラム(黒い影)は、哲也という「強力な観測者」の矛盾に耐えきれず、ノイズを撒き散らしながら一瞬だけ動作をフリーズさせた。
「立て、涼! 走れ!!」
哲也は硬直している涼の胸ぐらを掴み、強引に引きずり起こした。 フリーズは長くは続かない。彼らは再び、雨の降りしきる迷宮(東京)へと転がり出た。
「ハァ……ハァ……哲也、今のは……」 走りながら、涼が喘ぐように聞いた。
「システムは、僕たち観測者の『認識』に依存している」 哲也の瞳には、かつて理論物理学に向き合っていた時と同じ、いや、それ以上の鋭い光が宿っていた。 「僕たちが『世界は確固として存在する』と強く観測(信じる)限り、システムは矛盾を防ぐために物理法則を維持せざるを得ない。僕たちの『意識』そのものが、システムに対するハッキングの武器になるんだ」
雨は激しさを増していた。 追われる身となった二人の物理学者は、自分たちが依って立つ「現実」そのものと闘うことを認識した。