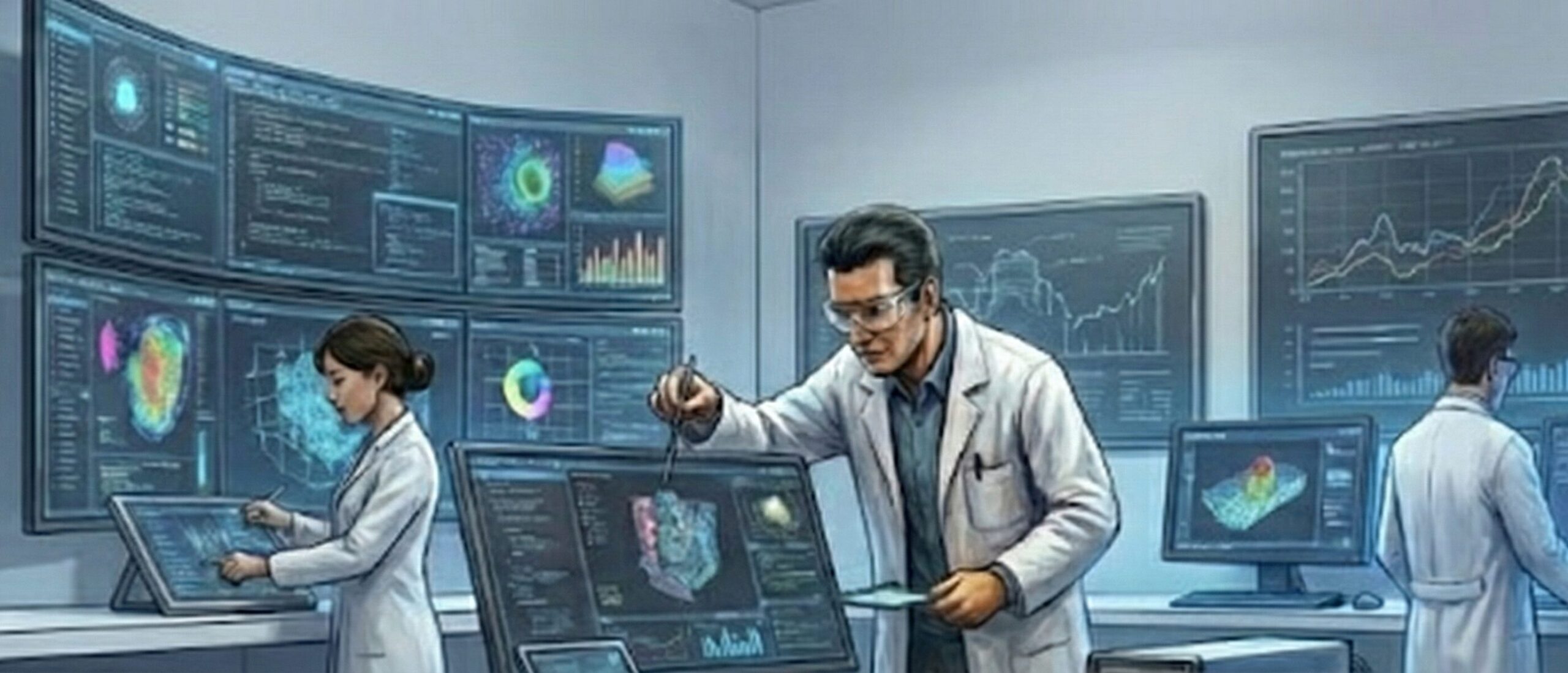第9話:波束の収縮と、繋がる手
ザッ、ザッ、ザッ、ザッ。
背後から迫る足音には、人間の生み出す「揺らぎ」が一切欠落していた。
靴底が水たまりを叩く水飛沫の上がり方すら、寸分違わず三回繰り返される。振り向かなくとも、佳奈(かな)には分かっていた。あの三人組のサラリーマン――システムが哲也という異常変数(バグ)と連携する佳奈を排除するために差し向けたターミネーターたちは、歩幅一つ変えずに、一定の速度で彼女を追尾している。
(怖い……! なによこれ、なんなのよ!)
激しい雨が容赦なく佳奈の体温を奪っていく。
肺が悲鳴を上げ、濡れたアスファルトに足を取られそうになる。しかし、背後の「彼ら」は息一つ乱していない。加速も減速もせず、まるで空間の座標データ()を一定の数式に従って等速で書き換えているだけのように、無機質に距離を詰めてくる。
渋谷の喧騒から外れた、薄暗い高架下の路地。
哲也から指定された「錆びついた非常口の扉」は、暗闇の奥に確かに存在していた。
「あそこ……っ!」
佳奈が扉に向かって手を伸ばした、その瞬間だった。
彼女の視界を覆っていた「現実のテクスチャ」が、唐突に剥がれ落ちた。
コンクリートの壁の染み、アスファルトのひび割れ、散乱するゴミ。それらの色彩(RGBデータ)が一瞬にして明度ゼロの黒へと変換され、次いで、空間そのものを構成する三次元の骨組み――ポリゴンのワイヤーフレームが剥き出しになったのだ。
「え……?」
佳奈の足が止まった。
物理的な「重力」が消失し、自分が上下左右の感覚を持たない虚無の空間に放り出されたような、強烈な目眩が彼女を襲う。
『[Warning] 対象の観測プロトコルに致命的な矛盾。オブジェクト【Kana】のメモリ領域を解放します』
背後から、三つの合成音声が完全に重なって響いた。
振り返ると、ワイヤーフレームの空間の中で、のっぺらぼうになった三人組が佳奈に手を伸ばしていた。
その指先が、佳奈の肩に触れた。
冷たい、のではない。
「無」だった。
肩を掴まれた部分から、自分の肉体の感覚が『消失』していく。痛みも、寒さも、恐怖すらも。自分の存在を定義していた「記憶」のファイルが、端からシュレッダーにかけられていくような、圧倒的な喪失感。
(私……消え、る……?)
佳奈の意識がブラックアウトしかけた、まさにその刹那。
目の前の虚空から、本来そこにあるはずのない「錆びた鉄扉」が、強烈なノイズとともにバキィッ!と弾け飛んだ。
「佳奈ッ!!」
暗闇の奥から、力強い腕が伸びてきた。
それは、佳奈の消えかかっていた右手を、痛いほど強く握りしめた。哲也の手だった。
その瞬間――。
パァァァン!! という、落雷が間近に落ちたような轟音が路地裏に響き渡った。
佳奈の視界で、ワイヤーフレームに分解されていた世界が、猛烈な速度で「再レンダリング」された。コンクリートの壁が質感を持ち、雨粒が再び重力に従って落下し、路地裏の泥水の匂いが鼻腔を突く。
佳奈の肩を掴んでいたターミネーターは、強烈な矛盾(エラー)に耐えきれず、ノイズの塊となって空中に霧散していた。
「哲也……っ!」
「こっちだ! 走れ!」
哲也は佳奈の腕を引き、地下への暗い階段へと彼女を強引に引きずり込んだ。
背後で重い鉄扉を閉め、内側からかんぬきをかける。
外の世界からの光と音が完全に遮断され、冷たく澱んだ地下共同溝の静寂が、三人を包み込んだ。
「ハァ……ハァ……哲也、今のは……今の、人たちは……」
佳奈はコンクリートの床にへたり込み、ガタガタと震えながら哲也のコートの袖を力強く握りしめた。その手は氷のように冷たかったが、哲也にはその震えが、何よりも尊い「生命の証」に思えた。
「大丈夫だ、佳奈。もう奴らは追ってこれない」
哲也は佳奈の背中をさすりながら、暗闇の奥でへたり込んでいる涼(りょう)に視線を向けた。
「見たか、涼。僕の仮説は正しかった。意識の量子もつれ(エンタングルメント)が、システムのガベージコレクション(削除処理)を強制的にキャンセルしたんだ」
涼は、幽鬼のような目で哲也と佳奈を見つめていた。
「……波束の収縮、か」
「そうだ」
哲也は、薄暗い赤色灯の下で、佳奈の手をしっかりと握ったまま言った。
「量子力学における『観測問題』。観測されていない素粒子は、あらゆる可能性が重なり合った『波』の状態で存在している」
哲也の口から、冷徹な物理の方程式が紡がれる。
「この数式が示す通り、状態は、複数の可能性 の確率的な『重ね合わせ』だ。シュレディンガーの猫と同じ。箱を開けるまで、猫は生きている状態と死んでいる状態が重なり合っている。しかし、僕たち『観測者』がそれを見た瞬間、波は一つの結果に収束(コラプス)し、現実が確定する」
哲也は、佳奈の震える肩を抱き寄せた。
「システムは、佳奈というデータを『消去する』という演算を実行しかけた。だがその瞬間、僕という別の観測者が、佳奈の手を握り、『彼女はここに生きている』と強烈に観測した。僕たちの意識が同期し、システムに対して【佳奈は存在する】という確定的な現実を突きつけたんだ」
「システムは……矛盾を嫌う」
涼が、震える声でその先を引き取った。
「もし佳奈を強引に消去すれば、彼女の存在を確定させてしまった哲也の『観測データ』と矛盾を起こし、宇宙のシミュレーション全体に致命的な論理エラー(パラドックス)が発生してしまう。だからシステムは、エラーを避けるために佳奈の消去処理を強制終了(アボート)せざるを得なかった……」
「そういうことだ。僕たちという『バグ』は、互いを観測し合うことで、システムに書き換えを許さない強固な『現実のネットワーク』を構築できる」
哲也の言葉は、絶望の淵に立たされた三人にとって、唯一の希望の光に思えた。
自分たちの「意識」や「感情」こそが、この張りボテの宇宙に対抗できる唯一にして最大の武器なのだと。
しかし、佳奈は哲也の胸に顔を埋めたまま、小さく首を振った。
「……ねえ、哲也。それって、本当に希望なの?」
「どういうことだい?」
「私、さっきあののっぺらぼうの人たちに触られた時……自分の記憶が、薄れていくのを感じたの」
佳奈の瞳には、システムの異常に対する恐怖だけでなく、もっと根源的な恐怖が宿っていた。
「もし私たちが、互いを観測し合うことでしか存在を証明できない『ただのデータ』なら……私たちが今まで過ごしてきた思い出も、この感情も、ただの【書き換えを拒否するためのセキュリティ・プログラム】に過ぎないってことじゃないの?」
その問いは、哲也の胸を鋭い刃のようにえぐった。
僕たちは、愛するから手を取り合うのか。それとも、システムから消去されないための「生存本能(アルゴリズム)」が、僕たちに愛という感情を『演算させている』だけなのか。
地下共同溝の冷たい水滴の音が、残酷なメトロノームのように響き続ける。
宇宙のソースコードを暴いてしまった彼らは、もはや「人間の尊厳」すらも、情報科学の冷徹な天秤にかけざるを得なくなっていた。
「……それでも」
哲也は、佳奈の手をさらに強く握りしめた。
「僕が君を大切に思うこの演算結果(こころ)だけは、絶対にシステムには渡さない」
三人の観測者は、エントロピーの死角たる地下の暗闇で、来るべきシステムとの全面対決に向けて、静かに身を寄せ合っていた。