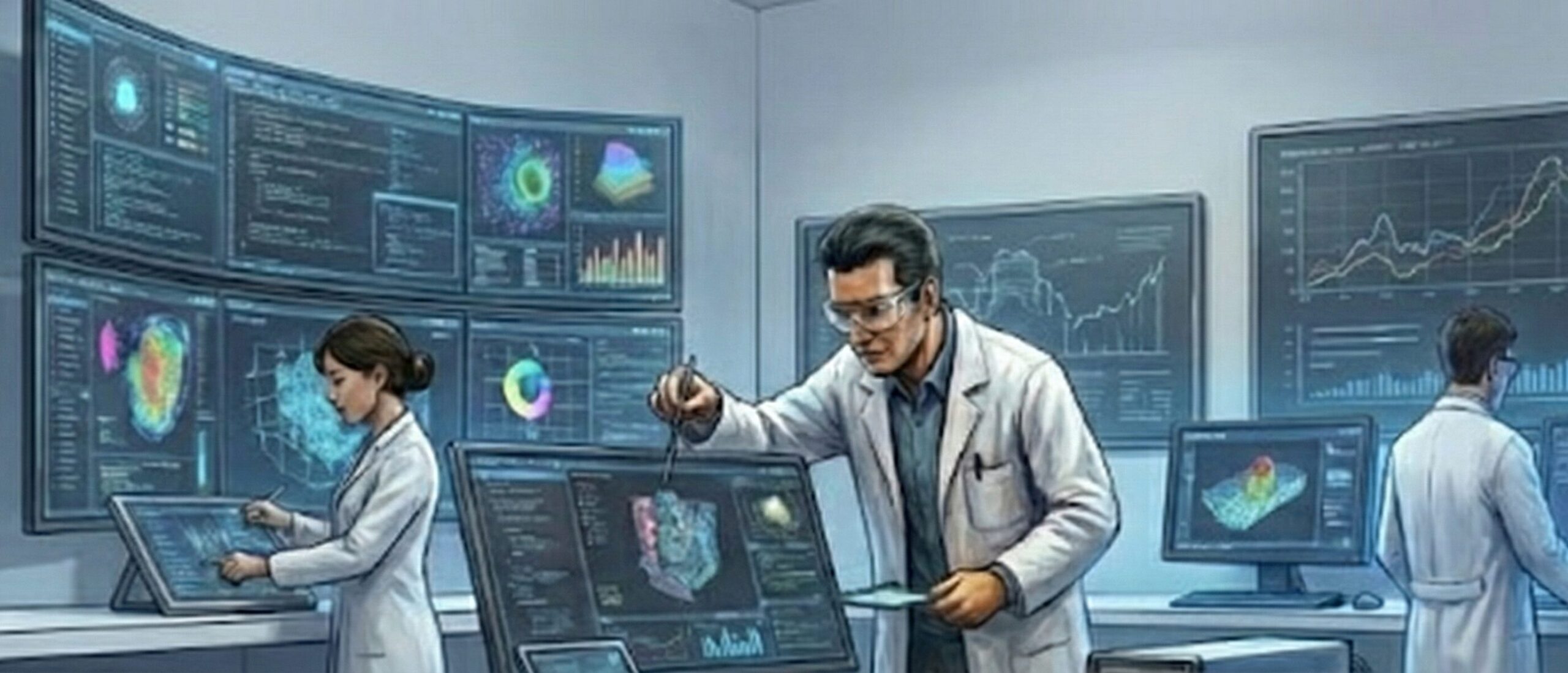第10話:感覚のハッキングと量子デコヒーレンス
渋谷の地下深く、巨大なコンクリートの共同溝。
エントロピーの底とも呼べるその閉鎖空間は、まるで世界の終わりから取り残されたシェルターのように、重く冷たい静寂に支配されていた。
ピチャン……ピチャン……。
天井から垂れる微かな水滴が、一定のリズムで水たまりを打つ。その単調な音だけが、今の彼らにとって時間が正常に流れていることを証明する唯一のメトロノームだった。
「……システムは、矛盾を避けるために僕たちの『削除』を保留した」
コンクリートの壁に背を預けながら、哲也は暗闇の中で静かに口を開いた。隣では佳奈(かな)が膝を抱え、その向こうで涼(りょう)が頭を抱えてうずくまっている。
「僕たちの『意識』が互いを観測し合い、量子もつれ(エンタングルメント)の状態にある限り、システムは僕たちを個別にデリートできない。だが、それは勝利じゃない。ただの『一時停止(ポーズ)』に過ぎないんだ」
「一時停止って……じゃあ、システムはどうやって私たちを消そうとするの?」
佳奈が震える声で尋ねた。
「エラーを起こさずに不要なファイルを削除するには、どうすればいいと思う?」
哲也は、自らの問いに答えるように、暗闇の空間を見つめた。
「共有されている『リンク』を切断すればいい。つまり、僕たちの【意識の同期】を解除し、それぞれを孤立した単独の変数(データ)に切り離すんだ」
その時だった。
「……おい。なんだよ、これ」
うずくまっていた涼が、唐突に顔を上げた。その声には、先ほどまでの恐怖とは違う、ひどく苛立ったような響きが混じっていた。
「どうした、涼?」
「暑いんだよ。さっきから、異常にな。空調のダクトでも壊れたのか? まるでサウナの中にいるみたいだ」
涼は着ていたジャケットを乱暴に脱ぎ捨て、ワイシャツの胸元を大きくはだけさせた。彼の額には、べっとりと不自然なほどの大量の汗が浮かんでいる。
しかし、哲也は眉をひそめた。
「暑い? 何を言ってるんだ。ここは地下二十メートルだぞ。むしろ、吐く息が白くなるくらい冷え切っているじゃないか」
「……え?」
佳奈も戸惑ったように涼を見た。彼女の唇は寒さで微かに青ざめており、哲也のコートをしっかりと羽織っている。
「涼くん、熱でもあるの? ここ、すごく寒いわよ」
「はぁ? お前ら、頭がおかしくなったのか!?」
涼は立ち上がり、暗闇に向かって怒鳴った。
「コンクリートの壁から熱気が放射されてるじゃないか! 水滴の音だってそうだ。さっきから、沸騰するみたいにボコボコ鳴ってるだろうが!」
涼の異常な剣幕に、哲也の背筋に氷のような悪寒が走った。
ピチャン、ピチャン。
哲也の耳には、冷たい水滴の音が等間隔で聞こえ続けている。沸騰する音など、どこにも存在しない。
(温度覚の異常。聴覚の不一致。これは……まさか)
哲也の脳内で、情報工学における一つのサイバー攻撃の手法と、量子力学におけるある現象が、最悪の形で結びついた。
「『中間者攻撃(Man-in-the-Middle Attack)』か……!」
哲也は床を蹴って立ち上がった。
「システムは僕たちを物理的に消せないから、今度は僕たちの『感覚(インターフェース)』を直接ハッキングしに来たんだ!」
「感覚をハッキング……?」
佳奈が怯えたように身を縮めた。
「僕たちがこの世界を認識しているのは、視覚や聴覚、皮膚感覚といった『データ』が脳に入力されているからだ。もしこの宇宙がシミュレーションなら、システムは僕たちの脳(意識)に送るその入力データを、個別に書き換えることができる。涼には『極端な熱と沸騰音』のデータを送り、僕たちには『寒さと水滴の音』のデータを送っているんだ!」
哲也は、涼に歩み寄ろうとした。
「涼、君が感じているその熱は幻だ! システムが君のパラメーターを書き換えて、僕たちの『観測の共有(現実の同期)』を破壊しようとしているんだ!」
「来るな!!」
涼は、近づこうとした哲也を激しく突き飛ばした。
「幻だと……? ふざけるな、哲也! 俺のこの肌を焼くような熱さも、汗も、全部データだっていうのか!?」
涼の眼球は異様に血走り、その視線はもはや哲也ではなく、何もない虚空の「何か」に向けられていた。実証主義の実験物理学者として、自らの「観測データ(五感)」こそを絶対の真理として生きてきた男にとって、感覚そのものを偽造されることは、精神の完全な崩壊を意味していた。
「……あ、あぁ……教授……?」
突然、涼が虚空に向かって震える手を伸ばした。
「涼! 何を見ている!」
「教授……! なんで、そんな姿で……違う、俺のせいじゃない……! 俺が、観測データを無視したわけじゃ……っ!」
涼は、誰の目にも見えない「白川教授の亡霊」に向かって、狂ったように弁明を始めた。
システムは、涼の脳内に直接、彼が最も恐れていた『罪悪感』のホログラムをレンダリングし始めたのだ。白川教授を絶望に追いやり、救えなかったという後悔。それを突くことで、涼の精神を内側から崩壊させようとしている。
「量子デコヒーレンス(量子干渉の消失)だ……」
哲也は床に倒れ込んだまま、絶望的な数式を頭に思い浮かべた。
「量子もつれ(エンタングルメント)にあるシステムは、外部の環境(ノイズ)と相互作用することで、そのもつれが破壊され、個別の古典的な状態に還元されてしまう」
哲也の口から、無意識のうちに物理学の真理が漏れ出す。
「システムは、涼の脳に強烈な『偽の環境ノイズ(熱や幻覚)』をぶつけることで、僕と佳奈との間の【意識の同期】を引き剥がそうとしているんだ! 涼の現実が僕たちと完全に切り離された瞬間、涼は孤立した変数になり……ガベージコレクション(削除処理)の対象に戻ってしまう!」
このままでは、涼が消される。
涼の意識が、彼だけの「狂った現実」に完全に閉じ込められてしまえば、哲也たちがどれほど「涼はここにいる」と観測しても、論理的なリンクは失われてしまう。
「涼くん!!」
佳奈が悲鳴を上げ、涼に駆け寄ろうとした。
だが、涼は錯乱状態に陥り、見えない亡霊から逃れるようにコンクリートの壁に頭を激しく打ち付け始めた。
「消えろ! 消えてくれ! 俺はデータじゃない! 俺は、俺はァァッ!!」
ゴッ、ゴッ、と鈍い音が響く。涼の額から、生々しい鮮血が飛び散った。
(赤い、血……。これも、システムが描画したテクスチャに過ぎないのか?)
哲也の理性が、冷酷にそう分析する。
すべては情報の書き換えだ。ならば、涼の「死」もまた、変数がゼロに収束するだけのアルゴリズムに過ぎない。僕たちに、彼を救うことなどできるのか? そもそも、この張りボテの宇宙で誰かを救うことに、何の意味があるというのか?
デカルトの命題が、再び哲也の脳内で響く。
『我思う、ゆえに我あり』
すべてが嘘でも、疑っている自分だけは本物だ。だが、それは究極の『孤独』の証明でもあった。自分以外の他者(涼や佳奈)が、本当に意識を持っているのか(哲学的ゾンビではないのか)、証明することは原理的に不可能なのだから。
「哲也! お願い、止めて!! 涼くんが死んじゃう!!」
佳奈の悲痛な叫びが、哲也の冷え切った思考を打ち砕いた。
佳奈は、血まみれになって暴れる涼を、細い腕で必死に抱きしめようとしていた。彼女は自分が幻かもしれないという恐怖を抱えながらも、目の前で苦しむ友人の「痛み」を、絶対的な現実として受け止めようとしていた。
その姿が、哲也にシステムの最も深い「バグ(真理)」を教えた。
(……そうか。システムが『痛み』や『感情』をわざわざ実装した理由。それは、孤立した変数を繋ぎ止めるための、強力な引力(グラビティ)だったんだ)
エントロピーが増大し、バラバラに崩壊しようとする情報の世界。
その中で、意識を持った観測者同士を結びつけるもの。物理学の重力は「情報の錯覚」に過ぎなかったが、心と心を結びつける「痛みという共感」こそが、この宇宙における真の重力だったのだ。
「涼ッ!!」
哲也は立ち上がり、血塗れになって暴れる涼に飛びかかった。
涼の拳が哲也の頬を激しく殴りつけ、口の中に鉄の味が広がる。物理シミュレーションがもたらす、圧倒的な『痛覚(ペイン・データ)』。
哲也は痛みに耐えながら、涼の襟首を掴み、その狂乱した瞳を真正面から睨みつけた。
「涼、僕の目を見ろ!! お前の見ている教授は幻だ! システムが送り込んだ不正なパッチデータだ!」
「離せッ! 教授が、教授が俺を責めてるんだ!!」
「違う! お前は実験物理学者だろうが!! なら、今お前を殴っているこの俺の『痛み』を観測しろ!!」
哲也は、涼の手を強引に掴み、自分の血の滲んだ頬に押し当てた。
「熱いか!? 僕の血は熱いか!? これがお前の現実だ! システムの偽造データなんかじゃない、俺が今ここで、お前と共に感じている【特異点(リアル)】だ!!」
『我思う、ゆえに我あり』ではない。
『我々が、共に痛む。ゆえに、我々はここに在る』。
哲也の強い意志(観測)と、佳奈の必死の抱擁。
二つの強固な意識のアンカーが、デコヒーレンス(量子干渉の消失)を起こしかけていた涼の意識を、強引に元の現実の座標へと引き戻し始めた。
「あ……、てつ……や……?」
涼の焦点の合わない瞳に、徐々に理性の光が戻ってくる。
彼を苦しめていた異常な熱気と沸騰音が、薄紙を剥がすようにスッと消失し、代わりに地下の底冷えする寒さと、冷たい水滴の音が戻ってきた。
「……ハァ……ッ、ハァ……俺は……」
涼はその場に崩れ落ち、哲也と佳奈の腕の中で、ボロボロと声を出して泣き崩れた。
システムによる「中間者攻撃(感覚のハッキング)」を、三人の意識のエンタングルメントが間一髪で退けたのだ。
しかし、安堵する時間は一秒も残されていなかった。
ピピッ、ピピッ。
哲也のポケットの中で、防水スマートフォンがけたたましい警告音を鳴らし始めた。
画面を開くと、システムからのエラーコードではない。それは、大学のサーバーに仕掛けておいた、哲也自作の「システム負荷監視プログラム」からのシステム状態観測の結果だった。
「……最悪だ」
スマートフォンの画面を照らす薄暗い光の中で、哲也の顔が絶望に染まった。
「システムは、僕たち三人の個別消去を諦めた。どうやら、宇宙の管理者(プログラム)は、この領域のエントロピー増大を『ハードウェアの限界』と判断したらしい」
「どういうことなの、哲也?」
佳奈が不安そうに身を寄せる。
「エラーを吐き続けるバグ(僕たち)が、システム全体に悪影響を及ぼすと判断されたんだ。……システムは、僕たちだけを消すのをやめた。この渋谷の地下一帯――半径3キロメートル四方の空間座標そのものを、完全に『初期化(フォーマット)』するつもりだ」
スマートフォンの画面には、渋谷を中心とした東京の重力場(空間の歪み)が、ブラックホールの事象の地平面に匹敵する極限の数値へと急上昇していくグラフが表示されていた。
宇宙の管理者は、この街ごと彼らを「無」に帰そうとしていた。