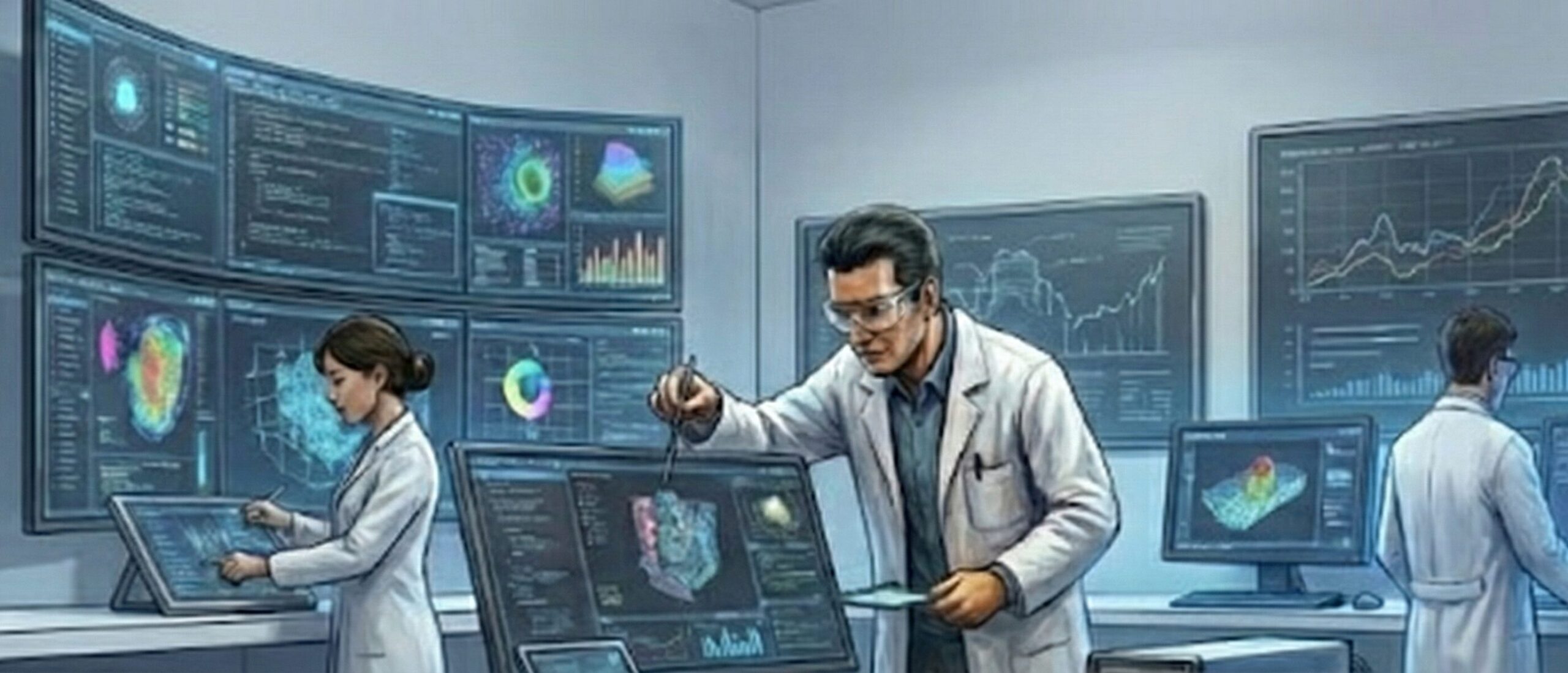第11話:空間のフォーマットと、ローカル変数のロック
渋谷の地下二十メートル。
暗闇に沈むコンクリートの共同溝で、哲也のスマートフォンの画面が狂ったように赤く点滅していた。
「半径3キロメートルの初期化……」
涼(りょう)が額から流れる血を拭うのも忘れ、絶望的な呻き声を漏らした。
「渋谷ごと、俺たちをデリートする気か。何万人いると思ってるんだ、地上の連中は……!」
「システムにとって、人間の数は関係ない。すべては一つの『環境変数』に過ぎないんだ」
哲也はスマートフォンをコートのポケットにねじ込み、佳奈(かな)と涼の腕を力強く掴んだ。
「急ごう。初期化のプロセスは、外縁部から中心に向かって進むはずだ。今すぐここを出て、システムがまだ『正常な描画領域』として保持している座標まで逃げ切る!」
「逃げるって、どこへ!?」佳奈が叫ぶ。
「地上だ。エントロピーの低いこの地下閉鎖空間は、真っ先にメモリ解放(削除)の対象になる!」
三人は、冷たい水たまりを跳ね上げながら共同溝を駆け出した。
だが、宇宙のシミュレーターが実行する初期化プロセスは、彼らの想像を絶する速度と異様さで迫っていた。
ピチャン、ピチャン、と一定のリズムで鳴っていた水滴の音が、突然「ピッ……ピピ……グゴ」という不快な電子音に変わった。
オーディオデータのサンプリングレートが強制的に下げられたのだ。
続いて、視覚の異常が訪れた。
非常灯の赤い光が滑らかなグラデーションを失い、ドット絵のような荒いブロック状の色彩(カラーパレットの減少)へと劣化していく。コンクリートの壁の精緻なテクスチャが剥がれ落ち、灰色ののっぺりとした単色のポリゴンに置き換わった。
「うわあっ!」
涼が足をもつれさせて転んだ。
彼が手をついた床のポリゴンは、すでに物理的な「硬さ(コリジョン)」のパラメータを失いかけており、涼の手首までがズブズブと床にめり込んでいた。
「涼! 引き抜け!」
哲也が涼の腕を力一杯引っ張る。ズポッという奇妙な音とともに腕が抜け、直後、その床の座標データは完全に「無(Void)」へと変換され、底知れぬ真っ暗な穴と化した。
「ひっ!」
「立ち止まるな! 空間の座標情報()が順番にゼロクリアされているんだ!」
階段を目指して走る三人。
周囲の空間は、もはや現実の模倣すら放棄していた。
上下左右の概念が狂い始める。彼らが走る通路の奥で、重力ベクトルが90度回転し、溜まっていた泥水が「壁」に向かって滝のように流れ落ちていく。アインシュタインの一般相対性理論が、たった一つのコマンド(format)で無残にスクラップにされていく光景。
「哲也! 階段よ!」
佳奈が指差す先に、地上へと続く非常用階段の鉄の扉が見えた。
三人は転がるように階段を駆け上がり、扉を突き破って地上(スクランブル交差点付近の路地)へと飛び出した。
だが、扉の向こう側に広がっていたのは、地獄絵図のようなバグの世界だった。
雨粒が空中で静止し、行き交う人々がマネキンのように硬直した異様な世界。
いや、硬直しているだけではない。
「ああ……嘘だろぉ……」
涼が膝から崩れ落ちそうになるのを、哲也は必死に支えた。
硬直した人々は、足元から徐々に「消滅」し始めていた。
血も肉も骨もない。彼らの体は、下から順番に透明なデジタルノイズへと変換され、空に向かって吸い込まれるように消えていく。彼らには「自分が消される」という自覚すら与えられていなかった。悲鳴一つ上げず、顔のテクスチャがバグで崩れたまま、ただ静かにデータ領域を解放されていく。
渋谷を埋め尽くすビル群も同様だ。
巨大なビルディングが、輪切りのようにスライスされ、その層ごとに虚無へと還元されていく。街頭ビジョンは砂嵐(ホワイトノイズ)だけを映し出し、それすらもすぐに電源を抜かれたように真っ暗になった。
初期化の波(フォーマット・ウェーブ)が、全方位から三人を包囲するように迫ってくる。
距離にして、あと数十メートル。
「逃げ道がない……!」
佳奈が哲也のコートを強く握りしめる。彼女の震えが、哲也の体に直接伝わってくる。
「哲也……私たちも、あんな風に消えちゃうの……?」
「消させない。絶対にだ」
哲也の眼は、崩壊していく街の光景を前にしても、決して屈服の光を宿していなかった。
「逃げるのが無理なら、システムをハックして、僕たちの周囲の空間だけを『初期化不可(Read-Only)』の領域にロックする!」
「ハックするって、どうやって!?」涼が叫ぶ。「相手は宇宙を構成しているスーパーコンピューターだぞ! 手元のスマホで対応する気か!?」
「いいや、僕たちの『意識』を使う」
哲也は、迫り来る虚無の波に向かって一歩前に出た。
「システムは、僕たちという高負荷な観測者(バグ)の処理を諦めて、空間ごとフォーマットしようとしている。つまり、今のシステムにとって、この領域は『データを上書きできる空き容量』として認識されているんだ」
哲也は、涼と佳奈に向き直った。
「佳奈、涼。僕の手に触れてくれ。そして、この『現実』を、お前たちの五感のすべてで、強烈に観測し続けろ」
三人は、互いの手を固く握り合った。
雨の冷たさ、互いの手の温もり、額から流れる血の匂い、心臓の鼓動。
「量子力学において、観測という行為は、重ね合わせの状態を『一つの現実』に収束(コラプス)させる。システムがこの空間のデータを『未定義(Null)』に上書きしようとするなら、僕たち三人の強固な意識(アンカー)を使って、この座標のデータを『書き換え不可能な確定した現実(Constant)』としてシステムに突き返し続けるんだ!」
初期化の波が、ついに彼らの数十メートル手前まで迫った。
アスファルトが消失し、虚無の暗黒が足元に迫る。
「我思う、ゆえに我あり!!」
哲也が魂の底から咆哮した。
「俺はここにいる!!」涼が叫ぶ。
「私は、絶対に消えない!!」佳奈も祈るように叫んだ。
三人の強烈な「観測(主観的現実の肯定)」が、量子もつれを通じて極大のデータパケットとなり、宇宙のシミュレーターへと逆流(フィードバック)した。
ギォンッ!!
空間が、断末魔のような軋み音を上げた。
三人の周囲、半径約五メートルの半球状の空間。
その境界線で、迫り来る虚無の波(フォーマット)が、見えない防壁に激突したようにピタリと停止した。
「……止まった……?」
涼が、信じられないものを見る目で呟いた。
「僕たちの意識が、この半径五メートルの空間座標のパラメーターをロックしたんだ。ローカル変数の固定化(スコープ・ロック)だ」
哲也は荒い息を吐きながら、冷や汗に塗れた顔を上げた。
彼らの周囲だけ、アスファルトが存在し、雨粒が落ち、三次元の物理法則が正常に機能している。
だが、その半球状の「現実のドーム」のすぐ外側は、完全にフォーマットされた絶対的な『虚無(無の空間)』だった。光すら存在せず、方向も時間も定義されていない、システムの未割り当て領域。
渋谷という街は、三人の立つ半径五メートルを残して、完全に世界からデリートされたのだ。
「……やりやがった」
佳奈が、震える足で崩れ落ちそうになる。
哲也の表情は、一瞬の安堵すら許容していなかった。
「システムは、スコープをロックしてフォーマットに抵抗した『不良セクタ』をそのままにはしておかない。プログラム上の物理法則による削除が無理だと悟れば、次はもっと直接的で、暴力的な『奴らにとっての免疫システム』を送り込んでくるはずだ」
哲也の視線の先。
彼らを囲む絶対的な虚無の暗闇の中に、数え切れないほどの「赤い点」が、不気味な明滅を始めた。
それは、物理法則(重力や慣性)に縛られない、純粋な『排除プログラム』の群れだった。
バグ(人間)を狩るために最適化された情報科学の申し子たちが、彼らの脆弱な「観察者のドーム」を取り囲もうとしていた。