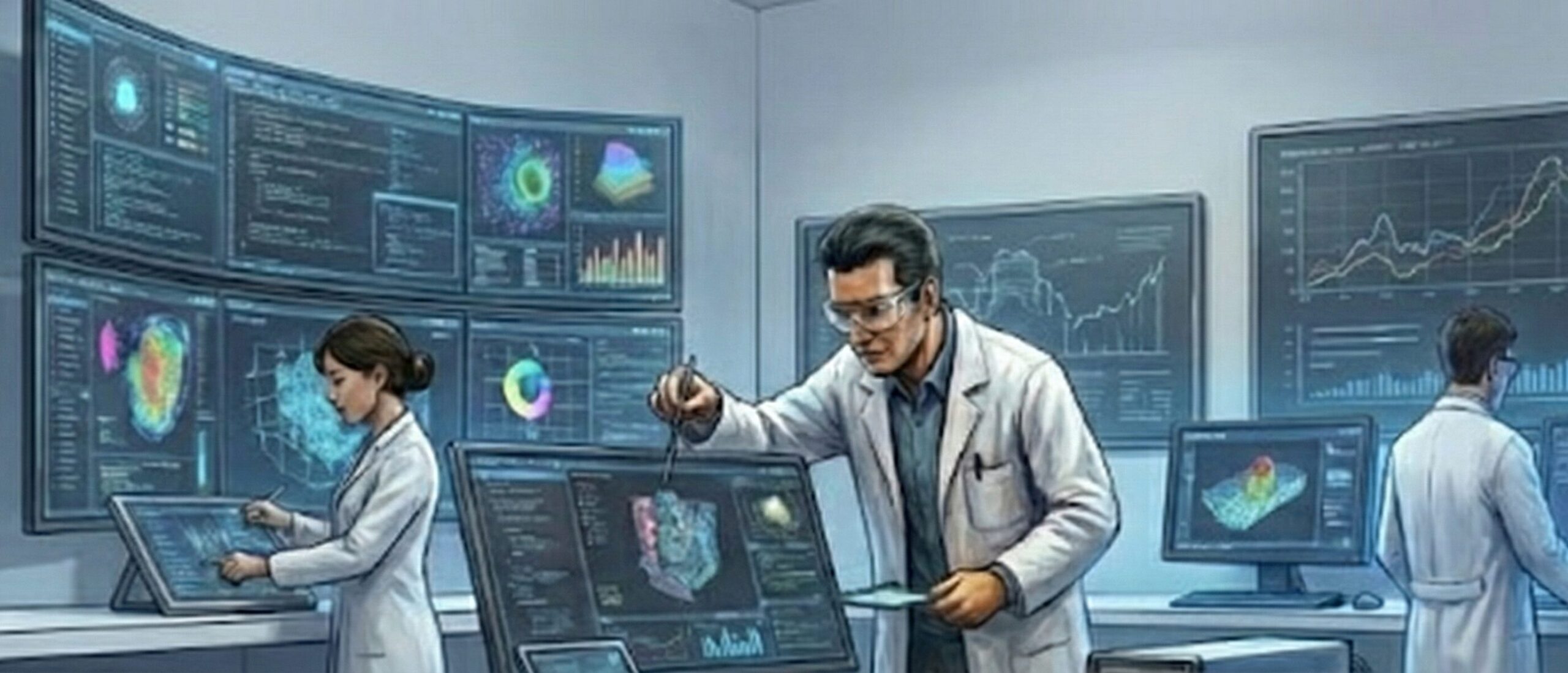第12話:虚無の猟犬と、サンドボックスの亡霊
半径五メートルの円形に切り取られたアスファルト。 それが、今や彼らに残された唯一の「現実」だった。
境界線の外側には、光も音も時間さえも存在しない、絶対的な未定義領域(Null)――システムのフォーマットによって生み出された虚無の海が広がっている。円形ドームの内側だけで、雨粒が重力に従って落下し、アスファルトの匂いが漂っていた。境界に達した雨粒は、そこで物理演算の対象外となり、パッと音もなく消滅していく。
「ハァ……ッ、ハァ……!」
哲也の呼吸は荒く、額からは冷や汗が滝のように流れ落ちていた。 涼(りょう)と佳奈(かな)の三人が互いの手を固く握り合い、強烈な意志(観測)によってこの「不良セクタ(現実のドーム)」のパラメーターを固定化(ロック)し続けている。 しかし、それは人間の脆弱なハードウェア(脳)に、スーパーコンピューターの演算処理を肩代わりさせるようなものだった。
ポタッ、と。 哲也の鼻筋を伝って、赤い雫がアスファルトに落ちた。鼻血だった。 涼も佳奈も、顔面は蒼白になり、小刻みに痙攣している。脳内のシナプスが異常なトラフィック(情報量)を処理しきれず、オーバーヒートを起こしかけていた。
「哲也……ッ! ドームが……縮んでるぞ……!」 涼が歯を食いしばりながら呻いた。
彼らがロックした半径五メートルの空間が、四・五メートル、四メートルと、じりじりと浸食され始めていた。 原因は明らかだった。 虚無の海に浮かぶ無数の「赤い点」。システムがこの不良セクタを物理的にデリートするために放った、ウイルス除去プログラムの群れだ。
「来るぞ……境界を、強く意識しろ!! ここは俺たちの領域だ、絶対に書き換えさせるな!!」 哲也が血の混じった唾を吐き捨てて叫んだ。
赤い点が、ドームの境界に殺到した。 その正体を間近で見た佳奈は、恐怖で喉の奥をヒュッと鳴らした。
それは、もはや先ほどののっぺらぼうの「人間の模造品」ですらなかった。 渋谷の街を構成していたデータ――砕けた信号機のテクスチャ、引き裂かれた車のタイヤのポリゴン、そして消去された数万人分の通行人たちの「手」や「髪の毛」のモデルデータ。それらが、システムによって無作為に継ぎ接ぎ(コンパイル)された、グロテスクな断片の塊だった。
『[Error] :不正な観測者を検知。強制ガベージコレクションを実行します』
何千もの混ざり合ったノイズ音声が、直接脳内に響く。 バグの猟犬(ハウンド)たちが、ドームの見えない壁に群がり、その鋭いポリゴンの爪で「現実」の境界線を削り取り始めた。
ガリィィィンッ!! 空間の座標データを書き換える、ガラスを引っ掻くような不快な演算音が響く。
「くそっ……! 負けるか……負けてたまるかよ!! 俺たちは観察者だ!!」 涼が咆哮し、猟犬が削り取ろうとする空間の座標を、強烈な実証主義の意志で「再定義(リロード)」する。剥がれかけたアスファルトが瞬時に修復され、猟犬の一匹が矛盾というエラーにより弾け飛んだ。
だが、数が多すぎた。 一匹を退けても、すぐに十匹が群がってくる。 三人の意識のネットワーク(量子もつれ)が限界を迎えようとしていた。佳奈の握る手の力が弱まり、彼女の膝がガクンと折れそうになる。
「佳奈! しっかりしろ! 意識を逸らすな!」 「ごめ、んなさい……頭が、割れそうで……っ!」 佳奈の目から、生理的な涙が溢れ出していた。彼女は物理学者ではない。ただの一般人が、宇宙のソースコードと直接殴り合っているのだ。限界はとうに超えていた。
ドームの半径が、三メートルにまで縮小する。 猟犬の放つノイズと、焦げたような電子の匂いがすぐそこまで迫っていた。 このままでは、押し潰される。ドームが崩壊すれば、彼らは瞬時に虚無へと分解され、「初めから存在しなかったデータ」として宇宙から消え去る。
その、絶望の淵で。
猟犬の群れの中に、一体だけ「異質な挙動」を示す個体がいた。 他の猟犬たちが狂ったように境界を攻撃する中、その一体だけは、ドームの壁に張り付いたまま、じっと哲也たちを見つめていたのだ。
それは、ポリゴンの破片とノイズで構成された歪な獣の形をしていた。 だが、その獣の表面に貼り付けられていたテクスチャの一部。
「……あれは」 涼が、信じられないものを見るように目を見開いた。
獣の右前足の部分に、擦り切れた黒い革のテクスチャが張り付いていた。 そして、その獣から発せられるノイズ音声の中に、他の無機質なエラー音とは明らかに違う、極めて人間的な、かすれた音声データが混じっていたのだ。
『……エントロピーは……増大する……』
「教授……!?」 哲也と涼の声が重なった。
間違いない。あの革のテクスチャは、白川教授が命よりも大切にしていた「革張りのノート」のデータだ。そしてあの音声は、教授の生体データからサンプリングされたものに他ならない。
「なんで……教授のデータが、アンチ・ウイルスなんかに混ざってるんだ!?」 涼が半狂乱になって叫んだ。 「教授はシステムに消されたんじゃなかったのか!? それとも、システムに取り込まれて、俺たちを殺すための兵器に作り変えられたって言うのかよ!」
「涼、落ち着け! 違う!」 哲也は、脳の血管が千切れそうなほどの激痛に耐えながら、物理学者としての冷徹な演算回路をフル回転させた。 「猟犬(ハウンド)は、システムが『不要になったゴミデータ(ガベージ)』を再利用して作った急造のプログラムだ。もし教授が完全にデリートされて無に帰したのなら、こんな風にデータが残っているはずがない!」
哲也の頭脳が、一つの希望の光(仮説)を弾き出した。
「教授のデータは、まだ消去されていない。システムは教授という『重度の特異点』を処理しきれず、完全な削除を諦めて、システムの最深部――隔離領域(サンドボックス)に幽閉したんだ! そして、隔離しきれずに漏れ出したテクスチャの破片だけが、こうしてアンチ・ウイルスの素材として使われている!」
「サンドボックス……隔離領域だって!?」 「ああ! パソコンでウイルスを検知した時、すぐに削除できない場合は『隔離フォルダ』に入れるだろう? それと同じだ。教授の意識(コアデータ)は、まだこの狂った宇宙のどこかに生きて幽閉されている!」
その言葉は、絶望しかけていた涼と佳奈に、強烈な「希望」という意識強化を施した。 教授が生きている。 このただのデータ処理の暗闇の中で、彼らの恩師が、まだ意識を保って孤独に戦っているかもしれないのだ。
「佳奈、涼! あともう少しだけ踏ん張れ!!」 哲也は二人の手を、骨が軋むほど強く握りしめた。 「ドームを維持したまま、移動するぞ!」
「移動するって……この虚無の中をか!?」涼が驚いた声で叫ぶ。
「この不良セクタ(ドーム)の座標変数を、僕たちの意志で書き換えてスライドさせるんだ。教授のデータの『欠片』が現れたということは、この虚無の海のどこかに、隔離領域(サンドボックス)へ繋がる坑道(バックドア)が存在するはずだ! そのリンクの欠片を逆に辿る!」
哲也は、眼前に迫っている「教授のテクスチャが張り付いた猟犬」を強烈に睨みつけた。
「俺たちが、この宇宙のカーネル(中枢)に乗り込んでやる。教授を取り戻し、このシミュレーションを回している『管理者』の正体を暴くんだ!」
「……上等だ、やってやろうじゃねえか!!」 涼の瞳に、かつてないほどの理性の炎が燃え上がった。実証主義の彼が、自らの意志でシステムの法則を書き換えることに同意したのだ。 佳奈も、涙で顔をぐしゃぐしゃにしながら、力強く頷いた。
「我思う、ゆえに……我ら在り!!」
三人の意識が完全にシンクロし、量子もつれが最大級のエンタングルメントを引き起こした。 半径三メートルまで縮小していたドームが、強烈な光を放ちながら再び五メートルへと膨張し、群がっていた猟犬たちを一気に弾き飛ばす。
そして、アスファルトの円形ドームは、絶対的な虚無の暗闇の中を、一つの独立した「箱船」として、未知の座標空間へ向けてゆっくりと滑り始めたのだった。