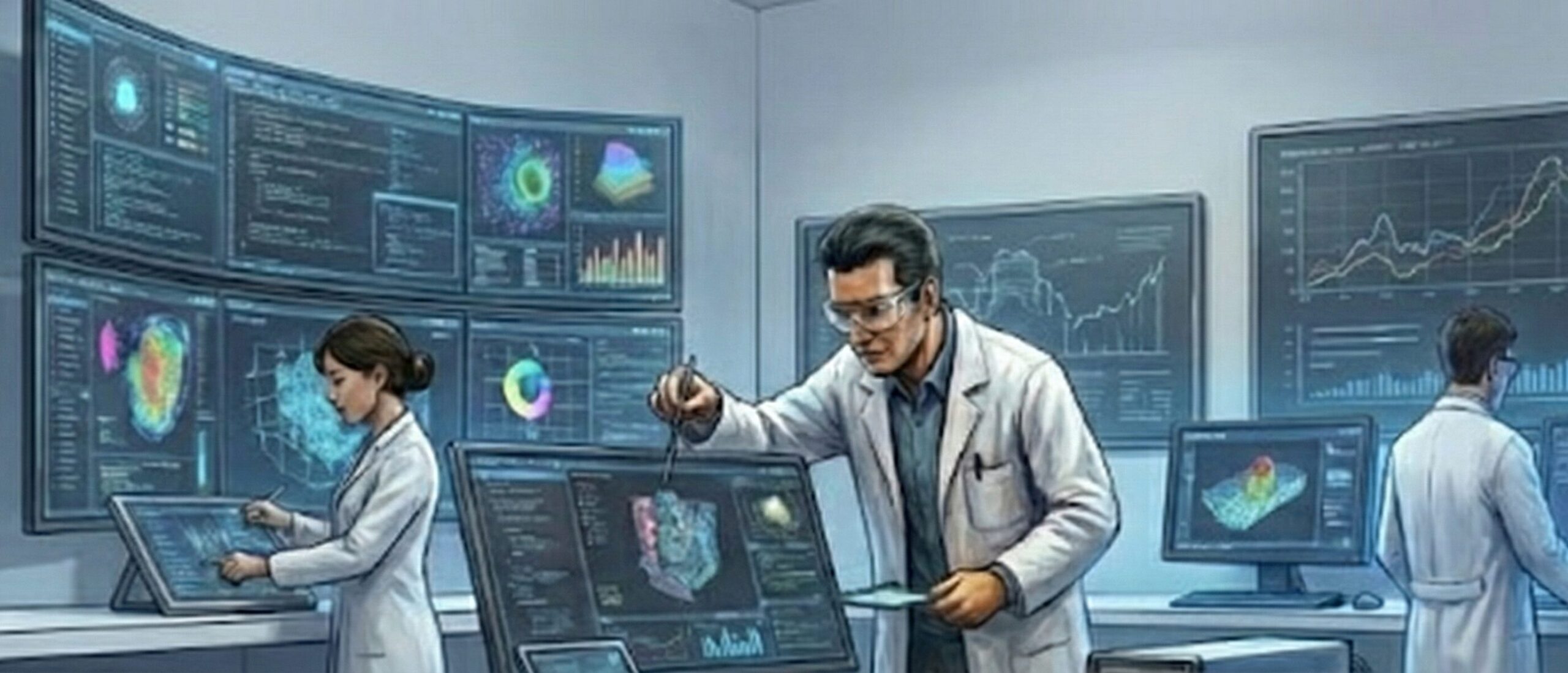第7話:エントロピーの死角と、地下迷宮
冷たい雨が打ち付ける渋谷のスクランブル交差点を背に、哲也と涼は狂ったようにアスファルトを蹴っていた。
「ハァ……ッ、ハァ……! 哲也、どこへ向かっているんだ!?」
背後からついてくる涼の息は完全に上がっていた。無理もない。実験室の椅子と計算機の前で三十年間を生きてきた男にとって、物理法則が崩壊した狂気の世界を全力疾走するなど、悪夢以外の何物でもない。
「情報量が少ない場所だ!」
哲也は振り返らずに叫んだ。
「ここはダメだ! 信号機、ネオンサイン、数千人の人間のモーションデータ、雨粒の流体力学! この渋谷という空間は、宇宙のシミュレーターにとって『エントロピー(情報の乱雑さ)』が極限まで高い、超・高負荷エリアなんだ!」
哲也の視界の端で、またしても世界が「カクッ」とコマ落ちした。
すれ違った酔っ払いのサラリーマンの顔面テクスチャが、一瞬だけロードしきれずに、のっぺらぼうの灰色のポリゴンとして表示されたのだ。
システムは今、哲也と涼という「自らを虚構だと認識してしまった致命的なバグ」を排除しようと、ガベージコレクタ(黒い影)を走らせている。だが、この圧倒的な情報量の渦の中では、システム側もリアルタイムで世界をレンダリング(描画)しつつ、バグを正確に特定して消去するのに凄まじい計算リソースを消費しているはずだ。
「隠れるなら、システムが『計算をサボっている』空白地帯(ロー・ポリゴン・エリア)に行くしかない!」
哲也が目指していたのは、渋谷駅の地下深く、迷宮のように入り組んだ巨大な地下空間だった。
さらに言えば、一般人が行き交うコンコースではない。空調設備や高圧電流のケーブルが這い回る、人間が立ち入らない「バックヤード」だ。
二人はセンター街を抜け、人目のつかない雑居ビルの裏手から、地下鉄の換気塔に繋がる重い鉄扉の前に辿り着いた。関係者以外立入禁止の黄色いステッカーが貼られている。
「鍵が……かかってるぞ!」
涼が扉のノブをガチャガチャと揺らしたが、鉄扉はびくともしない。
背後の路地裏の闇が、再びモザイク状に歪み始めた。
光が吸い込まれ、あの絶対的な黒を纏った「影」が、空間の座標をスキップしながら迫ってくる。
「涼、どけ!!」
哲也は涼を突き飛ばすと、鉄扉のノブを両手で力一杯握りしめた。
そして、眼を血走らせながら、強烈な意志を持って扉の向こう側の『空間』を観測(イメージ)した。
(鍵のシリンダーは存在しない。摩擦係数はゼロ。この扉は、ただの『開くという状態(変数)』を持っているだけのオブジェクトだ……!)
「我思う、ゆえに……開けぇッ!!」
哲也の認識が、システムの物理演算に強引なパッチを当てた瞬間。
バキィッ! という金属が内部から破断する甲高い音とともに、絶対に開くはずのない重厚な鉄扉が、まるで紙切れのようにあっさりと内側へ吹き飛んだ。
「……狂ってる」
涼は腰を抜かし、自分の手が震えているのを見つめた。
今、哲也は物理的な「力(ニュートン力学)」を使わずに、システムの「状態変数」を自分の意識で直接書き換えたのだ。それはもはや、物理学者の所業ではなく、この現実という仮想空間におけるハッカー(魔法使い)の振る舞いだった。
「急げ! 中へ!」
哲也は涼の襟首を掴み、暗闇の広がる地下階段へと引きずり込んだ。
背後で鉄扉を閉め、内側から太い鉄パイプをかんぬき代わりに差し込む。直後、扉の向こう側から、あの黒い影が空間を削り取るような無機質な衝突音が数回響いたが、やがてその気配はフッと途絶えた。
「……撒いた、のか?」
暗闇の中、涼が震える声で尋ねた。
「ああ。一時的にな」
哲也は壁を手探りし、非常用の薄暗い赤色灯のスイッチを入れた。
そこは、コンクリート剥き出しの巨大な地下共同溝だった。無数の太いパイプが動脈のように走り、水滴が一定のリズムで反響している。太陽の光も、雨音も、人間の喧騒も一切届かない、絶対的な閉鎖空間。
「ここは、システムにとっての『死角』だ」
哲也はコンクリートの冷たい床に座り込み、荒い息を整えた。
「死角……?」
「エントロピーの定義を思い出せ、涼。ルートヴィッヒ・ボルツマンが残した、統計力学の最も美しい墓碑銘だ」
哲也は、薄暗い床の埃を指でなぞり、一つの短い方程式を書いた。
「 はエントロピー、 はボルツマン定数。そして は、その系が取り得る『微視的な状態の数』だ。この式が意味するのは、情報が複雑で多様であるほど、エントロピーは増大するということ」
哲也は指先を床から離し、周囲の無機質なコンクリートの壁を見渡した。
「地上のスクランブル交差点は、(状態の数)が無限大に近い。誰がどこへ歩くか、雨粒がどう弾けるか、システムは毎秒天文学的な演算を強いられている。だが、この地下空間はどうだ? 変化する要素は、落ちる水滴と、換気扇の回転だけだ。極めてエントロピーが低い(情報量が少ない)」
「……そうか」
涼の顔に、ようやく物理学者としての理性の光が少しだけ戻った。
「情報量が少ないということは、システムがこの空間を維持するための『演算コスト(負荷)』が極端に低いということだ。だから、システムはこの地下空間の監視を『スリープ状態』に近い低頻度のクロックに落としている。ガベージコレクタ(影)が追ってこれないのは……」
「システムが、この空間の座標データを高解像度でレンダリングしていないからだ。僕たちは今、コンピューターのメモリの『使われていない空き領域』に隠れ込んだのと同じ状態にいる」
二人の間に、冷たく重い沈黙が降りた。
自分たちの生存戦略すらも、情報工学のアルゴリズムに依存しなければならないという絶望的な事実。
「なぁ、哲也」
涼が、両膝を抱え込んでぽつりと呟いた。
「俺たちがこうして隠れている間にも、システムは俺たちを消去しようとログを漁っているんだろう。もし俺たちが消されたら……地上の連中は、俺たちのことをどう思うんだ? 『白川教授と同じように失踪した』と悲しむのか?」
哲也は胸の奥が冷たくなるのを感じた。
「……いや。おそらく、最初から『存在しなかったこと』にされる。システムの不整合を防ぐために、僕たちに関するすべてのデータ――戸籍も、論文も、誰かの記憶の中の変数すらも、綺麗に書き換えられるはずだ」
「俺の三十年間の人生が、ただの『なかったこと』になるのか……」
涼の目から、ついに限界を超えた涙がこぼれ落ちた。
「ふざけるなよ。俺は痛いんだ。怖いんだ。こんなに心臓がうるさいのに、これが全部ただのデータ処理だなんて、誰が納得できるっていうんだ!」
暗い地下道に、男のむせび泣く声が響いた。
哲也は涼に掛ける言葉を持たなかった。彼自身もまた、同じ絶望の淵に立っているのだから。
しかし、哲也は立ち上がった。
ポケットから、防水仕様のスマートフォンを取り出す。画面にはノイズが走り、電波状況は極めて不安定だったが、微かにアンテナのマークが点滅していた。
「涼。絶望するのは、僕たちの『意識』の正体を暴いてからだ。システムがなぜ、これほどまでに不合理な『感情』や『痛み』を持つ観測者を必要としたのか。そのバグの正体に、僕は一つだけ心当たりがある」
哲也は、震える指でディスプレイをタップした。
コール音が、ノイズ混じりに一度、二度と鳴る。
『……もしもし、哲也?』
スピーカーの向こうから、佳奈(かな)の戸惑うような声が聞こえた。
その声を聞いた瞬間、哲也の冷え切っていた胸の奥に、確かな「熱」が灯るのを彼は自覚していた。
「佳奈。無事か? 今、どこにいる」
『どこって……まだ大学の近くの喫茶店よ。雨がひどくて帰れなくて。あなたこそ、急に飛び出していってどうしたの? 声がすごく切羽詰まってるわ』
「いいか、佳奈。よく聞いてくれ。絶対に信じられないだろうが……」
哲也は言葉を切った。
もしこの世界がシミュレーションなら。自分という観測者が、世界を『現実』として確定させているのなら。
佳奈という「他者の意識(もう一人の観測者)」と強く結びつくこと(量子もつれ)こそが、この脆弱な現実をシステムから防衛し、自分たちの存在を繋ぎ止める最大のアンカー(錨)になるはずだ。
「佳奈。君のその『感情』が、世界を救う鍵になるかもしれない。今から言う場所へ来てくれ。……誰の目にもつかないように」
コンクリートの冷たい牢獄の中で、哲也は世界というシステムに対する、ささやかで、しかし最も危険な「反逆のコード」を書き始めようとしていた。