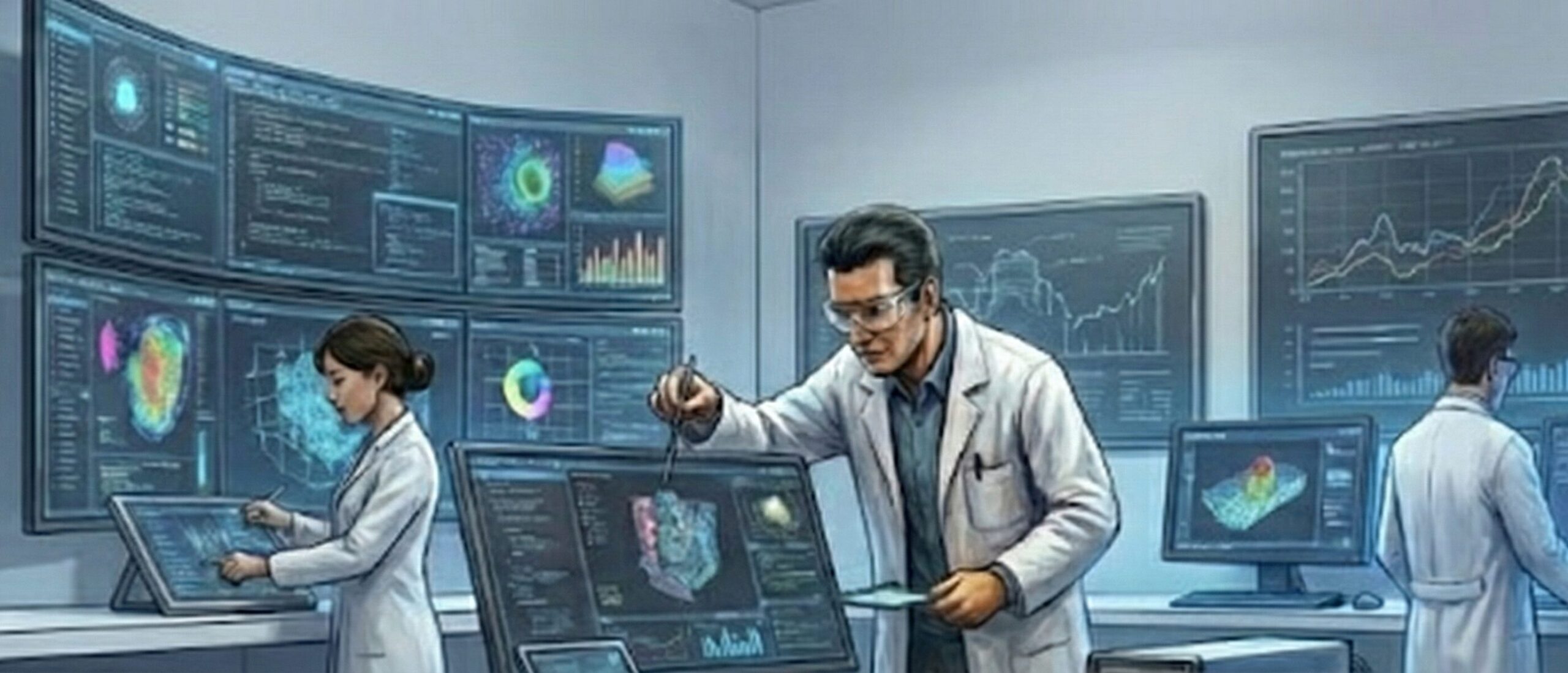第14話:停止性問題と、箱庭の亡霊
絶対の防壁であった事象の地平面が、哲也(てつや)の紡いだエントロピーの数式に応答し、静かに円形の入り口(バックドア)を開いた。
「……行くぞ」
哲也を先頭に、涼(りょう)と佳奈(かな)は互いの手を固く握りしめたまま、歪んだ空間の膜を通り抜けた。 ゼリー状の冷たい粘膜を突き破るような、強烈な不快感が全身を舐め上げる。自分たちの肉体を構成する座標データが、強引に別のフォーマットへと変換(エンコード)されていく感覚。
そして次の瞬間、三人の靴底は、固いリノリウムの床を踏みしめていた。
「ここは……」 佳奈が、恐る恐る目を開けた。
そこは、彼らがよく知る場所だった。 壁一面を覆う膨大な専門書、散乱する計算用紙、パイプ煙草の甘く重い匂い。間違いなく、T大学理学部棟の最上階にある白川教授の研究室だ。 だが、窓の外の景色は、東京の摩天楼ではなかった。窓ガラスの向こうには、ただ真っ白な「無(Null)」だけが広がっている。
「サンドボックス(隔離領域)……。システムが、メインの宇宙から完全に切り離して構築した、閉鎖されたテスト環境だ」 哲也は、張り詰めた空気の中で周囲を見渡した。
部屋の中は、奇妙な静寂に包まれていた。 空中に舞う埃の粒子が、完全に静止している。壁に掛けられた振り子時計の秒針は、「カチッ」と音を立てて進むが、次の瞬間には元の位置に逆戻りし、永遠に同じ一秒間を往復し続けている。
物理学における「閉じた時間線(Closed Timelike Curve)」。 この部屋の時間は、過去から未来へ流れていない。システムが設定した極めて短い時間枠の中を、無限にループしているのだ。
「教授……! 教授、どこにいるんですか!!」
涼が、静止した空間に向かって叫んだ。 その声がトリガーとなったかのように、部屋の奥――山積みにされた専門書の陰から、ギギギ……と不自然な機械音を立てて、革張りの椅子が振り返った。
「……空間の、最大情報量が、三次元の体積ではなく、二次元の表面積によって上限を決定される。それはすなわち……」
椅子に座っていたのは、白川教授だった。 だが、その姿を見た涼は、息を呑んで後ずさった。
教授の肉体は、半ば「透過」していた。 輪郭がノイズでブレており、古いアナログテレビの電波障害のように、彼の顔や手には幾度も横縞のグリッチが走っている。
「……空間の、最大情報量が、三次元の体積ではなく、二次元の表面積によって上限を決定される。それはすなわち……」
教授は、哲也たちの方を見向きもせず、手元の革張りのノートにペンを走らせながら、全く同じ言葉を、全く同じ抑揚で繰り返していた。
「教授! 俺です、涼です! 助けに来ました!」 涼が駆け寄ろうとしたが、哲也がその肩を強く掴んで引き止めた。
「待て、涼! 触るな!」 哲也の顔は、苦痛と悲哀に歪んでいた。 「あれは……もう、僕たちが知っている白川教授じゃない。システムが教授の『思考のプロセス』を解析するために、メモリの残骸から再構築した……ただの実行可能ファイル(エグゼキュタブル)だ」
「実行可能ファイルって……教授は生きているんじゃなかったのかよ!」
「システムにとって、教授は『宇宙の真理(ソースコード)にアクセスできる危険なマルウェア』だ。システムは教授を完全にデリートする前に、この隔離領域(サンドボックス)で彼を『実行』し続けているんだ。彼がどこまで宇宙の構造を解読していたのか、その思考アルゴリズムを解析し、システムの脆弱性を修正(パッチ)するために……!」
教授の虚ろな呟きが続く。
「……空間の、最大情報量が、三次元の体積ではなく……」
無限ループ(while (true))。 白川教授という偉大な物理学者の精神は、絶望の真理に辿り着いたその瞬間のまま、この狭い箱庭の中で、システムに監視されながら永遠に同じ演算を繰り返させられていたのだ。 人間の尊厳に対する、これ以上ない冒涜だった。
「ふざけんな……。ふざけんなよ、クソッタレのシステムが!!」 涼の目から、大粒の涙が溢れ出した。 実証主義の彼が、自分の恩師がただの「バグのサンプル」として扱われている現実に、心が引き裂かれていた。
「涼くん……」佳奈も口元を手で覆い、涙を流した。
だが、哲也は一人、冷徹な物理学者の眼で教授のループ現象を観察していた。
(なぜ、システムは教授の思考を『解析』する必要がある?) 宇宙を統べる全知全能のシミュレーターならば、内部のデータ(人間)が何を考えているかなど、一瞬でスキャンできるはずだ。わざわざサンドボックスを構築し、時間をループさせてまで、教授のプログラムを「走らせて」挙動を観察している理由。
情報科学における最大の未解決問題。 アラン・チューリングが証明した、コンピューターの絶対的な限界。
「……停止性問題(Halting Problem)か」
哲也の呟きに、涼が涙を拭いながら振り返った。 「停止性問題……? どんなプログラムでも、それが最終的に停止して答えを出すか、それとも無限ループに陥るかを、実行する前に判定することは数学的に不可能である、というあれか?」
「そうだ」 哲也は、透過して明滅する教授の姿を見つめながら、静かに歩み寄った。
「いかに宇宙のシミュレーターが巨大でも、コンピューターである以上、チューリングマシンの限界からは逃れられない。システムは、教授という複雑なプログラム(意識)が、最終的に『どんな結論(バグ)を吐き出すか』を、事前に予測できなかったんだ。だから、隔離して実際に走らせる(実行する)しか方法がなかった」
哲也の脳内で、バラバラだったピースが恐ろしい勢いで繋がり始めた。
「……分かったぞ。システムが、なぜ『意識』というバグをわざわざこの宇宙に実装したのか」 哲也の声が、微かに震えていた。 「システムは、自分自身では計算できない『停止性問題』や、非決定論的な多項式時間(NP)の問題を解かせるために……この宇宙を構築したんだ。僕たち人間は、ただのキャラクターじゃない。システムの計算能力の限界を超えるための、ヒューリスティックな演算ノード(直感的な計算機)として生み出されたんだ!」
「人間が……計算機……?」 佳奈が戦慄したように呟く。
「そうだ。だからシステムは、僕たちに『痛み』を与え、『感情』を与え、『死への恐怖』を与えた。極限状況下で、人間の意識という量子コンピューターが、予測不可能な『最適解』を導き出すことを期待して……!」
その時だった。
「……空間の、最大情報量が……」 無限に繰り返されていた教授の声が、唐突に止まった。
ギギギ……と、ノイズまみれの顔が、ゆっくりと哲也の方へ向けられた。 焦点の合っていなかった教授のガラス玉のような瞳に、一瞬だけ、かつての深い知性と、人間としての強烈な「自我」の光が宿った。
『……てつ……や……くん……か……?』
「教授!」 哲也は、ためらうことなく、透過している教授の肩を強く両手で掴んだ。
バチィィィンッ!! 量子もつれ(エンタングルメント)による、強烈な意識の同調。哲也の『痛み』と『現実感』が、教授の閉じたループのコードに強制的な割り込み(インタラプト)をかけたのだ。
教授の肉体の明滅が、一瞬だけピタリと止まり、はっきりとした質量を取り戻した。
『あぁ……哲也くん……涼くんも……。すまない……私は、絶望のあまり……自ら、データの海に……身を投げてしまった……』 教授の頬を、ホログラムではない本物の涙が伝った。 彼は、自分自身がすでに現実から切り離された亡霊であることを、はっきりと自覚していた。
「教授、助けに来ました! 僕たちが、あなたをここから出します! 観測を同期させれば……!」 哲也が叫ぶが、教授は静かに首を振った。
『駄目だ……。私は、深淵を覗きすぎた……。私のコードは、すでにシステムによって……不可逆な暗号化(ハッシュ化)を受けている……。外に出れば、私は……完全なノイズになって、君たちを巻き込む……』
部屋の壁が、ミシミシと嫌な音を立て始めた。 哲也たちがバックドアを開けて侵入し、教授のループを破壊したことで、サンドボックス自体がシステムの再起動プロセスに入ろうとしていたのだ。 窓の外の白い「無」が、禍々しい赤い光に染まり始めている。
『……時間がない……。哲也くん、聞いてくれ……』 教授は、哲也の手を震える力で握りしめ、何かを託そうとした。
『この宇宙は……巨大な計算機だ……。だが、管理者(アドミニストレータ)は……システムの内側にはいない……』 教授の顔に、再び強烈なノイズが走り始める。システムによる強制デリートが始まったのだ。
『……重力の井戸を……下れ……』 教授の口から、最後の数式が血とともに吐き出されるように紡がれた。
『すべての計算の起点……Root(ルート権限)は……宇宙の底……極限の、特異点(シンギュラリティ)に……ある……。そこへ、行け……! 我思う、ゆえに……!!』
ザァァァァァァッ!!
閃光とともに、白川教授の姿は無数の光のピクセルへと分解され、哲也の手の中から完全に消滅した。 革張りのノートも、膨大な専門書も、部屋のすべてがポリゴンの塵となって崩れ落ちていく。
「教授ゥゥゥッ!!」 涼の悲痛な叫びが、崩壊するサンドボックスのノイズの中に吸い込まれていった。
「ここはもう保たない!! 脱出するぞ!!」 哲也は、教授の消えた空間から「あるもの」を強く握りしめると、涼と佳奈の腕を引き、崩壊する部屋の壁――彼らが開けたバックドアの座標へ向かって、全力で床を蹴った。