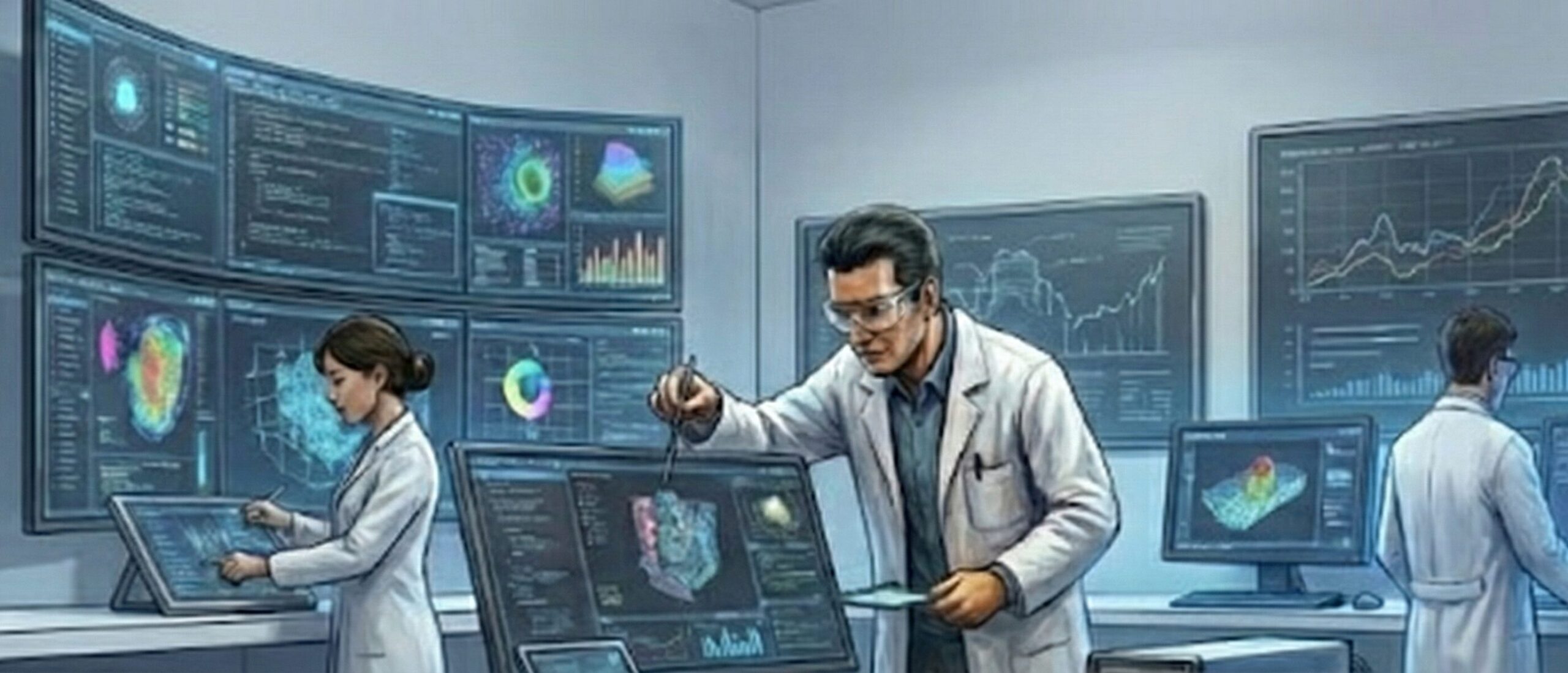第15話:事象の地平面からの生還と、託されたコード
ザァァァァァァッ!!
白川教授の隔離領域(サンドボックス)を構成していたすべての物理モデルが、原初のデジタルノイズへと還元されていく。 本棚が、デスクが、そして教授自身が存在した空間の座標が、乱数表の嵐に巻き込まれたようにランダムな文字列へと分解され、真っ赤な虚無の渦へと吸い込まれていった。
「走れ!! 後ろを振り向くな!!」
哲也(てつや)は、涼(りょう)と佳奈(かな)の腕を両手で引きちぎれんばかりに掴み、彼らがこじ開けたバックドア(事象の地平面の裂け目)に向かって跳躍した。 足元のリノリウムの床が、彼らが踏み切った瞬間にコリジョン(当たり判定)を失い、底なしの暗黒へと変貌する。
「うおぉぉぉぉッ!!」 涼が、物理法則の消失に対する本能的な恐怖から絶叫した。佳奈は目をきつく閉じ、哲也の腕にすがりついている。
三人の体が、歪んだ空間のゼリー状の膜に突っ込む。 行きと違って、帰りのプロセスはシステムによる「強制イジェクト(排除)」の力が加わっていた。彼らの肉体を構成するペタバイト級の量子データが、猛烈なG(重力)を伴って圧縮され、光ファイバーのケーブルを高速で打ち出されるような、内臓が裏返るほどの強烈な加速度を伴った。
ブワァァァンッ!!
空間の膜を突き破り、三人は固い地面に激しく叩きつけられた。
「ガハッ……! ゲホッ、ゴホッ!」 哲也はアスファルトの上を数メートル転がり、全身の骨が軋むような衝撃に肺の空気をすべて吐き出した。隣では涼が激しくむせ返り、佳奈がうずくまって肩で息をしている。
「……ハァ、ハァ……戻って、きたのか……?」 涼が、擦り剥いた腕を押さえながら顔を上げた。
そこは、彼らが防衛していた半径五メートルの「現実のドーム」の内部だった。 しかし、状況は最悪のままである。 システムは隔離領域(サンドボックス)の崩壊と同時に、この不良セクタに対する攻撃を一旦リセットしたらしかった。ドームを取り囲んでいた猟犬(排除プログラム)たちの赤い光は消え去っている。
だが、ドームの外側に広がっていた「フォーマットされた虚無の海」には、新たなテクスチャが貼り付けられようとしていた。
「見ろ、哲也……。システムが、空間を『再構築』している……」 涼の震える指先が、ドームの外を指し示した。
渋谷の街が、ものすごい速度で再レンダリングされていた。 アスファルトが敷き詰められ、ビルが下から上へと建ち上がり、電柱が立ち上がる。 しかし、それは彼らが知っている「渋谷」ではなかった。
ビルの形状は、計算リソースを極限まで節約した、テクスチャの貼られていない灰色の直方体の集合体(プレハブ)だった。窓ガラスの反射演算は省略され、看板の文字は意味をなさないアルファベットの羅列になっている。 そして何より異様なのは、再構築されたその街を歩き始めた「通行人」たちだった。
顔がない。服の色もすべて同じグレー。 関節の動きを最小限に抑えた、初期状態のモデリング人形(デフォルト・アバター)のような何万もの群衆が、完全に無音のまま、一定の速度で交差点を直進しているのだ。
「……低解像度の、セーフモードか」 哲也はよろめきながら立ち上がり、システムの意図を悟った。 「僕たちというバグのせいで、システムはこの領域に割ける演算リソースを使い果たしたんだ。これ以上の致命的エラーを避けるために、物理演算もAIのアルゴリズムも極限まで間引いた『最低限の環境』で再起動をかけたんだ」
「なんて不気味な光景だ……まるで死者の街じゃないか」 涼が吐き捨てるように言った。
「哲也……あなたが、さっきの部屋で握りしめていたものって……?」 佳奈が、哲也の固く握られた右手に視線を落として尋ねた。
哲也はハッとして、自分の右手を開いた。 サンドボックスが崩壊し、白川教授のデータが塵となって消える直前。哲也は、教授が手放した「革張りのノート」のデータを、強烈な観測の力で自分たちのローカル変数(現実)へと引きずり込んでいた。
彼の手のひらにあったのは、一冊の古いノート……ではなかった。
「……USBメモリ?」 涼が目を丸くした。
哲也の手の中にあったのは、物理的な質量と金属の冷たさを持った、古びたUSBフラッシュメモリだった。表面には、教授がノートの表紙に書いていたのと同じ、乱雑なイニシャルが刻まれている。
「メタファー(隠喩)の変換だ」 哲也は、そのメモリを指先でつまみ上げた。 「あの隔離領域で、教授の意識は『ノートに数式を書く』というメタファー(動作)を通じて、システムの深淵のログを記録し続けていた。それを僕たちのこの三次元の物理環境に持ち出した時、システムが矛盾を補完するために、この時代に最も適した『記憶媒体』のオブジェクトへと再レンダリングしたんだ」
「つまり、その中に……教授がサンドボックスで解析した、システムの根幹に関わるデータが入っているってことか?」
「ああ。教授は最後に言った。『重力の井戸を下れ。すべての計算の起点(Root)は、宇宙の底、特異点にある』と」
哲也はポケットから自分のスマートフォンを取り出した。画面はひび割れていたが、電源は生きていた。幸い、スマートフォンのインターフェースはまだ正常に機能している。哲也はUSBメモリをスマートフォンに接続した。
画面にパスワードの入力画面が現れる。 哲也は迷うことなく、教授が最後に紡いだ数式を打ち込んだ。 『』
カチッ、という音とともに、ロックが解除された。 画面に表示されたのは、たった一つのファイル。それは膨大な数式の羅列ではなく、三次元の座標データと、ある施設の図面だった。
「これは……」 涼が画面を覗き込み、息を呑んだ。 「日本の地下深部に建設された、重力波干渉計の施設……! 俺たちに最初の『空間のノイズ』のデータを送ってきた、あの巨大地下施設じゃないか!」
「KAGRA(カグラ)の系譜を継ぐ、最新鋭の地下観測所……」 哲也の瞳に、鋭い光が宿った。
「なぜ、あそこなんだ? あそこには巨大なレーザー干渉計と真空パイプがあるだけで、スーパーコンピューターの中枢があるわけじゃないぞ?」
「涼。アインシュタインの一般相対性理論において、重力とは何か。空間の歪みだ。そして、重力波とは、その空間の歪みが波として伝わる現象だ」 哲也は画面の図面を拡大した。
「僕たちが暴いた真理(ホログラフィック原理)によれば、重力は『情報のエントロピー増大』がもたらす錯覚に過ぎない。だとすれば、重力波を観測するあの巨大な干渉計は、システム側から見れば何になる?」
涼の顔から血の気が引いた。 「……空間の歪み(情報のエントロピーの変化)を、最も高精度に検知するセンサー。つまり、宇宙のシミュレーターの『エラー監視ポート(デバッグ・ターミナル)』か!」
「その通りだ」 哲也はスマートフォンを握りしめ、顔を上げた。 「システムは、宇宙全体の演算の整合性を保つために、各地に『重力の井戸』……つまり、情報を極限まで吸い寄せる特異点(デバッグ用のアクセスポイント)を配置している。あの地下施設は、人類が偶然作り上げたものじゃない。システムが、空間の歪み(演算エラー)を監視するために、我々人類の科学の発展を誘導して『作らせた』ハードウェアなんだ」
「システムに作らされた……。じゃあ、あそこの最深部に行けば……」
「管理者権限(Root)に繋がる、メインのコンソールがあるはずだ」 哲也の言葉には、もはや一抹の迷いもなかった。
「僕たちの肉体がデータに過ぎなくても。この痛みが、システムのプログラムしたアルゴリズムだとしても。僕たちをこの箱庭の中で走らせ、教授を永遠のループに閉じ込めた『管理者』の顔を拝むまでは、俺の意識(バグ)は絶対に停止しない」
佳奈が、哲也と涼の手を強く握った。 「行きましょう。私たちの『存在』の答えが、そこにあるなら」
三人は、灰色の人形たちが無音で行き交うセーフモードの渋谷を背に、日本の地下最深部――重力の井戸を目指す、最後の過酷な旅へと足を踏み出した。