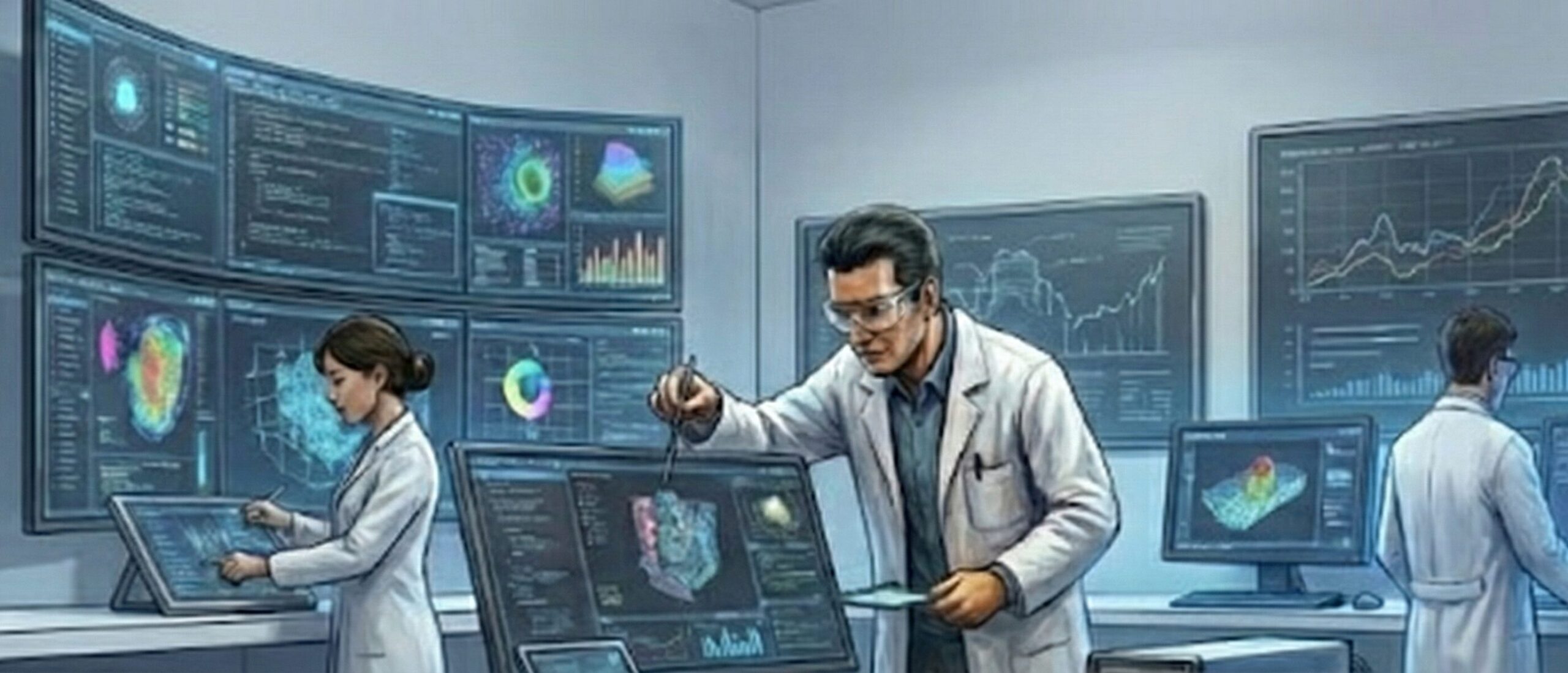第8話:意識のエンタングルメント
冷たく、無機質な水滴がコンクリートの床を打つ音が、渋谷の地下深く、巨大な共同溝の暗闇に等間隔で響き続けていた。
「佳奈、今から言うルートを通って、渋谷駅の地下最深部――副都心線のさらに下にある、旧搬入用トンネルまで来てくれ。地上の改札は通るな。人目につかない非常階段を使うんだ」
スマートフォンを握りしめる哲也の指の関節は、白く変色するほど力が入っていた。
ノイズ混じりの通話の向こう側で、佳奈が息を呑む気配が伝わってくる。
『哲也、本当にどうしたの? あなた、まるで何かに追われているみたいな……』
「追われているんだ。僕たちじゃない、『この世界』そのものにな。説明している時間はない。いいか佳奈、道中、決して周囲の人間――いや、通行人の『目』を見ないでくれ。彼らに認識されるな」
通話を切った哲也は、背後の壁にずり落ちるようにして座り込んでいる涼(りょう)を見下ろした。
涼は、極度の恐怖とアイデンティティの喪失によって、抜け殻のように虚空を見つめている。
「……彼女を巻き込む気か、哲也」
涼の唇が、微かに動いた。
「俺たちはバグだ。システムからマークされた異常な変数だぞ。佳奈と接触すれば、彼女までガベージコレクタ(排除プログラム)の標的にされるかもしれないんだぞ」
「逆だ、涼」
哲也はスマートフォンのバックライトを消し、絶対的な暗闇の中で親友に向けて静かに言い放った。
「僕たち二人の『観測』だけでは、システムに書き換えられてしまう。この脆弱な現実(データ)をシステムから防衛し、僕たちの存在を繋ぎ止めるには、外部の『強固なアンカー(錨)』が必要なんだ」
「アンカーだと……?」
「量子もつれ(エンタングルメント)だよ」
哲也は、暗闇の中で一本の指を立てた。
「二つの素粒子が一度でも相互作用すると、それらは『もつれ』の状態になる。片方のスピンが上向き()と確定した瞬間、もう片方はどれほど距離が離れていようと、瞬時に下向き()と確定する。アインシュタインが『不気味な遠隔作用』と呼んで忌み嫌った現象だ」
哲也は、コンクリートの床に微かな水滴で数式を描くように指を動かした。
「量子力学において、もつれ合った二つの粒子は、別々の存在ではなく『一つの不可分なシステム』として振る舞う。これを、情報科学の視点――この宇宙のシミュレーターの都合で考えてみろ」
暗闇の中で、涼の息遣いがわずかに変わった。物理学者としての本能が、哲也の論理の行き着く先を予測し始めていた。
「システムが、ある『バグ(僕たち)』のデータをデリートしようとしたとする。しかし、そのバグが他の『正常な変数(佳奈)』と強固な量子もつれ……すなわち、深い感情や記憶で結びついていたらどうなる?」
「……矛盾が生じる」
涼が、掠れた声で答えた。
「片方のデータを勝手に消去すれば、もつれ合っているもう片方のデータとの間に、論理的な不整合(パラドックス)が発生する。システムは、エラーを出さずに僕たちを消すために、佳奈のデータ……いや、佳奈と関わりのある世界中のすべてのデータを同時に書き換えなければならなくなる」
「その通りだ」
哲也は力強く頷いた。
「意識のエンタングルメント。それが僕たちの生存戦略だ。佳奈が僕たちを『そこにいる』と強烈に観測し、僕たちと感情を共有する限り、システムは彼女という存在の膨大な演算プロセスを巻き込まない限り、僕たちを消去できない。彼女の強い『自我(私)』が、僕たちを現実に縛り付ける重石になるんだ」
システムが最も演算負荷を強いられる「意識」というバグ。
それをネットワークのように結びつけることで、システムの排除アルゴリズムに過負荷(オーバーロード)を強いる。それが、哲也が導き出した唯一の防衛策だった。
その頃、地上では。
大学近くの喫茶店を出た佳奈は、激しい雨に打たれながら、スマートフォンの地図アプリを頼りに渋谷方面へと向かっていた。
(哲也……あなた、一体何に巻き込まれているの?)
彼女の胸の奥で、言い知れぬ不安が黒い染みのように広がっていた。
幼い頃から知っている哲也は、物理の数式に取り憑かれたような男だが、決して冗談で人を怯えさせるような人間ではない。彼のあの「世界が崩壊する」とでも言いたげな切羽詰まった声が、佳奈の耳から離れなかった。
地下鉄の入り口へ向かうため、人通りの少ないガード下を歩いていた時のことだ。
ピピッ、ピピッ、ピピッ。
佳奈の耳に、奇妙な電子音が聞こえた。
それは、彼女のスマートフォンの通知音ではなく、空間そのものから直接鳴っているような、無機質で不快なノイズだった。
ふと、前方から歩いてくる三人組のサラリーマンに目が留まった。
ビニール傘を深く差した彼らは、横並びになってこちらへ向かってくる。
(……え?)
佳奈は足を止めた。
彼らの歩き方が、異常だったのだ。
三人とも、右足を踏み出すタイミング、腕を振る角度、傘を持つ手の傾きが、「完全に一致」していた。まるで、コピー機のボタンを三回連続で押して出力された、寸分違わぬクローンのように。
ザッ、ザッ、ザッ。
水たまりを踏む音すらも、一つの音声ファイルを再生しているように重なっている。
『決して周囲の人間の目を見るな。彼らに認識されるな』
哲也の警告が、脳裏にフラッシュバックした。
佳奈は恐怖で喉が引きつるのを感じながら、壁際に寄り、彼らをやり過ごそうとした。
だが、三人組は佳奈の数メートル前で、唐突に「ピタリ」と停止した。
慣性の法則を完全に無視した、不自然極まりない急停止だった。
そして、三人の首が、まるで機械のモーターが回るように、全く同じ速度でギギギ……と佳奈の方へ向けられた。
傘の下から覗く彼らの顔。
そこには、表情が存在しなかった。怒りも、悲しみも、疑問もない。ただ、焦点の合わないガラス玉のような瞳が、佳奈という存在を「スキャン」するように見つめている。
『[Query] 未定義の接続を検出。対象の観測プロトコルを検証します』
三人のサラリーマンの口が同時に開き、合成音声のようなノイズ混じりの言葉が吐き出された。
それは人間の言葉ではなく、システムが変数(佳奈)の異常を検知し、チェックサム(データ照合)を実行している音だった。
「ひっ……!」
佳奈は悲鳴を飲み込み、踵を返して逆方向へと走り出した。
背後で、三人のサラリーマンが「全く同じモーション」で反転し、佳奈を追いかけてくる足音が響く。
(何なの、これ!? この人たち、人間じゃない!)
雨が容赦なく佳奈の体を叩く。
世界が、狂っている。哲也の言っていたことは真実だった。この東京という街は、人間が生きるための場所ではなく、恐ろしい「何か」が支配する巨大な箱庭なのだと、佳奈の直感が悲鳴を上げていた。
彼女は、哲也が待つ地下迷宮への入り口――錆びついた非常口の扉を目指して、泥水を跳ね上げながら狂ったように走り続けた。
彼女の胸にある「哲也を助けたい」という強烈な感情(意識)だけが、システムによる書き換えに抗う、唯一の盾となり得た。